江戸幕府の成立から100年ほどが過ぎた18世紀(元禄〜寛政期)になると、官僚的性格を帯びた武士階層は武力ではなく教化による統治を求められるようになった。そのため、各藩では儒学を修めた上層庶民(儒者)を「藩儒」として召し抱えた。近世における儒者は身分制の枠組みに収まらない存在であり、ときに身分間移動をも果たす中間知識層であった。本書では、多くの儒者を輩出した龍野藩(現在の兵庫県たつの市近辺)の藩儒・股野玉川に関する一次史料を参照しながら、近世の藩儒・藩校と現実政治の関わりを読み解いていく。
序章 本研究の課題と方法
1. 本研究の課題
2. 先行研究の到達点と問題点
3. 龍野藩と龍野藩儒の概観
4. 本研究の構成と依拠する史料
第一章 諸藩における儒者登用の動向と<藩儒の家>の形成
1. 諸藩における最初の藩儒
2. <藩儒の家>の形成
3. <藩儒の家>の待遇と継承
4. 藩需を補佐した者たち
第二章 藩儒の修学過程と公務
1. 藩儒の修学過程
2. 藩儒の公務
3. 他藩の事例
第三章 藩儒の社会的役割と文化的ネットワーク
1. 藩儒の社会的役割
2. 他藩・他地域の学者とのネットワーク
3. 大坂懐徳堂との関係
4. 他藩の事例
第四章 龍野藩における藩校の成立・展開と藩儒の役割
1. 天明末年〜寛政初年における藩士およびその子弟の教育
2. 寛政末年以降の御対面所講釈と武芸稽古所
3. 文化初年の藩校設立構想
4. 天保年間における敬楽館の成立とその後の展開
5. 幕末維新期の敬楽館における教育の実態
6. 他藩における藩校の「成立」
終章 本研究の成果と今後の課題
1. 本研究の成果
2. 今後の課題
参考文献一覧
あとがき/初出一覧
主要人名索引
新着の本 すべて見る

灼熱カバディ(27)

灼熱カバディ(26)

灼熱カバディ(25)

灼熱カバディ(24)

灼熱カバディ(23)

灼熱カバディ(22)

灼熱カバディ(21)

ふしぎな さーかす
30日間で人気のまとめ記事 すべて見る
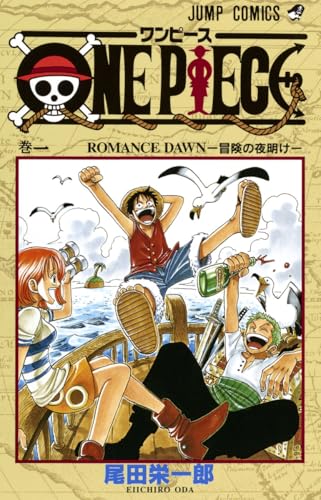





小説のまとめ記事 すべて見る






自己啓発のまとめ記事 すべて見る
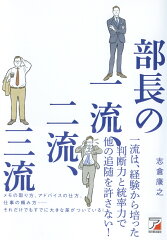


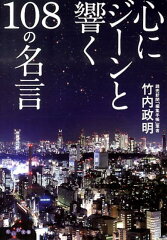

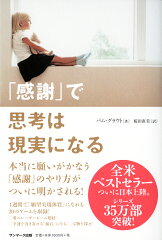
趣味のまとめ記事 すべて見る






漫画のまとめ記事 すべて見る



















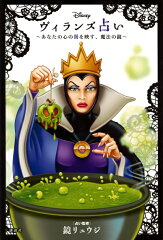
![ヤングマガジン 2026年12号 [2026年2月16日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/516Te9JKoxL._SL500_.jpg)


![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL500_.jpg)











