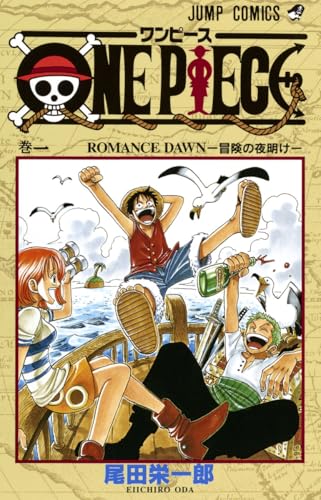「ひとつの体を共有する双子の華麗なる遍歴」とストーリーを聞いてパリの貴族の家に生まれたシャム双生児の話だと思ってたんですが違いました。でも例の浴槽ドボンまで「バルタザールの正体って実は人面瘡?」と疑ってた馬鹿な私。
この物語はメルヒオールの手記という形で幕を開けるのだが、作中に挿入されるバルタザールの反論というか突っ込みというか、それがとてもいい味出していて面白い。
メルヒオールの言い分に「そうじゃない」「誤解だ」「なんてことだ、まだあの時の事を根に持ってるのか?」と合いの手を入れるバルタザール、なんたって同じ体を共有してるからその気になればむりやり手を乗っ取って訂正を挟む事が出来る。
げに便利な二人羽織り漫才にくすっと笑ってしまう。
とても流麗で端正な文体なのだが、本書の魅力はそのエスプリとユーモアにあると思う。
兄弟がシュトルツに注ぐ意地悪な視線、女にふられてやけくそになった挙句の放蕩三昧の日々、初めて駱駝に乗ったときの公爵にあるまじきはしゃぎっぷり、金髪のエックハルトの愛すべき小悪党ぶり……
文体の格調高さにもかかわらず、それらの描写が非常にツボを得ていて小気味いい。
「ぺぺと名前までつけていたのに!」と駱駝の誘拐を本気で口惜しがるさまに噴き出さずにいられようか。いや、無理。
そんなに難しく考えなくても一度このユーモアがツボに入ればすらすら読めるので心配なし。
続編とかでないかなあ。
坂道を転がり落ちるような凋落の一途さえいっそ清清しい二人のそれからが読みたい。



















![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL500_.jpg)