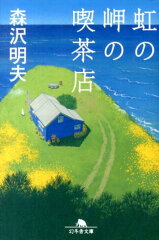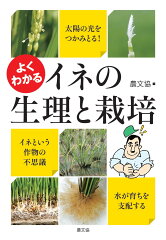出版業界や本に対する問題敵10選

本好きなみなさん、こんな経験ありませんか?読書中に「あれ?表紙と内容が全然違ってない?」と感じたことは。出版業界の波乱含みな事情を描いた小説や、文字通りの「本」に立ち向かう作品、10選ご紹介します。文字の魔力に導かれた者たちが織りなす物語、これを読めばもう、本棚を見る目が変わるかも?心を打つストーリーから、笑ってしまうようなエピソードまで幅広く揃えております。ただの物語ではなく、本という存在を見つめ直すきっかけを与えてくれるでしょう。
『本なら売るほど 1』

ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古本屋「十月堂」。
店主の人柄と素敵な品ぞろえに惹かれて、今日もいろんなお客が訪れる。
本好きの常連さん、背伸びしたい年頃の女子高生、
不要な本を捨てに来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人。
ふと手にした一冊の本が、思わぬ縁をつないでいくーー。
本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ贈る、珠玉のヒューマンドラマ!
漫画誌「ハルタ」連載時から大きな反響を呼んだ話題作が、待望のコミックス1巻発売です。
| 作者 | 児島 青 |
|---|---|
| 価格 | 792円 + 税 |
| 発売元 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2025年01月15日 |
『税金で買った本(1)』

小学生ぶりに図書館を訪れたヤンキー石平くん。10年前に借りた本を失くしていたことをきっかけに、あれよあれよとアルバイトすることに!
借りた本を破ってしまった時は? 難しい漢字の読み方を調べたい時は? ルールに厳しくも図書を愛してやまない仲間と贈る、読むと図書館に行きたくなる図書館お仕事漫画、誕生です!
| 作者 | ずいの/系山 冏 |
|---|---|
| 価格 | 792円 + 税 |
| 発売元 | 講談社 |
| 発売日 | 2021年12月20日 |
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか (集英社新書)』

| 作者 | 三宅香帆 |
|---|---|
| 価格 | 1100円 + 税 |
| 発売元 | 集英社 |
| 発売日 | 2024年04月17日 |
『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか : 知られざる戦後書店抗争史』
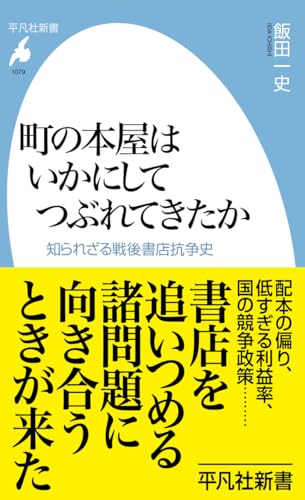
| 作者 | 飯田一史 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 平凡社 |
| 発売日 |
『さあ、本屋をはじめよう 町の書店の新しい可能性』

| 作者 | 和氣正幸 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 日販アイ・ピー・エス |
| 発売日 |
『重版出来!(1) (ビッグコミックス)』

| 作者 | 松田奈緒子 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 小学館 |
| 発売日 | 2013年11月04日 |
『出版帝国の戦争 不逞なものたちの文化史』

帝国日本の出版市場は合法/非合法を問わず、植民地の人々を積極的に読者として包摂しようとした。朝鮮人にとって日本語は抑圧する言語であり、抵抗の思想を学ぶための言語であり、娯楽のための言語でもあった。『戦旗』や『キング』、マルクスやレーニン、金子文子や火野葦平、林芙美子らの思考や文学が、発禁本とともに帝国の支配圏でいかなる思想や文化を醸成したのか、多彩な作品から読み解く。
はじめに
第一章 プロレタリア
「共産党宣言」と平民‥情報戦時代のスローメディア『平民新聞』‥「露探」と戦う平民行商たち‥「新/平民」と朝鮮人の曖昧な境界
第二章 図書館
焚書と「図書無館」の時代‥文化政治と朝鮮語の規範化‥帝国から/への向上心をあおる‥夜市・露店という空間
第三章 不逞鮮人
朝鮮統監政治の新造語‥帝国メディアと闇メディアの攻防‥法域の間隙と不穏な情報戦‥金子文子・朴烈と「太い鮮人」たち
第四章 検閲
「雨の降る品川駅」‥内地と日本語の両義的な役割‥検閲帝国の誕生
第五章 資本
発禁という付加価値ー雑誌『戦旗』と『蟹工船』‥雑誌『戦旗』と非合法商品の資本化‥ 非合法商品のカタログ、『戦旗』‥移動メディア「不逞鮮人」と植民地市場
第六章 植民地
山本実彦の満・鮮‥『改造』と『東亜日報』の宴会‥改造社から社会主義を学ぶ‥改造社の転向‥満・鮮という新商品
第七章 翻訳
内鮮一体の表象としての翻訳‥雑誌『文章』と内地からの「戦線文学選」‥帝国の小説家・林芙美子の戦線‥女たちの内鮮一体‥朝鮮の林芙美子=崔貞熙
第八章 戦争
旧帝国の総力戦と軍需株の暴騰‥「広場の孤独」と植民地・日本‥朝鮮(人)なき朝鮮戦争‥張赫宙の朝鮮戦争従軍記‥日本は誰の味方でもない
おわりに
| 作者 | 高榮蘭 |
|---|---|
| 価格 | 3520円 + 税 |
| 発売元 | 法政大学出版局 |
| 発売日 | 2024年05月20日 |
『本屋、地元に生きる = Bookstore,Living Locally』

| 作者 | 栗澤,順一,1972- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2023年02月 |
『江戸時代の貸本屋 庶民の読書熱、馬琴の創作を支えた書物流通の拠点』

江戸時代には書物を読むことのできる人びとが庶民にまで広がった。
その読書熱を支えた書物流通の拠点が貸本屋である。
読者の興味をそそり、見たことのない世界や名所旧跡へ連れ出す書物、
隠された秘密や真相を解き明かす書物、便利性に満ちた生活実用書ーー
これらをすぐに調えて手元に届けるのが貸本屋であった。
また、読書熱の高まり、さまざまなジャンルにわたる出版文化の広がりは、
近世における創作の場においても、大きな影響を与えた。
特にその浩瀚な知識を自らの作品に注ぎ込んできた近世を代表する作家・曲亭馬琴の日記には、
近世知識人と書物の関係をまざまざと伝える、特筆すべき内容がふんだんに含まれている。
長年にわたり諸資料を博捜してきた筆者が、
江戸時代の貸本屋の展開、そして、書物と人びととのかかわりの諸相を描き出す書籍文化史論。
はしがき
第一部 本のある風景
第二部 近世貸本屋の展開
一 貸本屋研究の意義
二 四民の読書熱
三 貸本屋の仕事
四 法制と貸本屋
五 作者・板元・貸本屋
六 読物流行の変遷と貸本屋
七 貸本屋と読者
まとめ
第三部 馬琴の書物探索と貸本領域
一 馬琴の書物愛
二 知識人との書物貸借
三 馬琴作品の愛読者たち
四 馬琴と貸本屋
五 馬琴の本屋探書
六 馬琴の写本製作
七 馬琴の潤筆料と生活
八 愛蔵書の売却
九 馬琴の疾病
十 わが庭は花盛りなれど……
まとめ
あとがき
| 作者 | 長友千代治 |
|---|---|
| 価格 | 5500円 + 税 |
| 発売元 | 勉誠社 |
| 発売日 | 2023年05月31日 |
『「ひとり出版社」は人生の楽園』

| 作者 | 山中伊知郎/著 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 飯塚書店 |
| 発売日 | 2020年05月25日 |
さあ、読書好きの皆さん、とうとうこの記事の締めがやってきました。「出版業界や本に対する問題敵10選」にピックアップした各作品をふまえ、改めて考えてみてください。それぞれの物語やキャラクターが抱える問題は、実は私たち一人一人が日々の生活の中で直面する課題や葛藤と重なっているかもしれません。
それは単純に本や出版業界にとどまらず、社会全般を問い直す契機となるはずです。誤解や偏見を超えて、本質的な議論を深めるきっかけとなれば、それだけでなく、世界をより良く、より理解しやすいものにしてくれるでしょう。
一冊の本が持っている力は、時に小さく、時には大きく、私たちの視点や価値観を変えることができます。それらはまるでドラマチックな瞬間を通じて我々に問いかけてくるパズルのようなもの。そしてそのパズルを解く過程が、私たち自身の成長や理解を深めるのです。
また、これらの作品を通じて、作家たちがどのような問題に取り組み、どのように表現に挑んだのかを見ることで、私たち自身も自己表現やコミュニケーションの方法を考え直す良い機会になるでしょう。
たとえ一部の人々しか直面しない問題であったとしても、物語を通じて理解し共感する力は、決して小さなものではありません。それは、世界に対する広い視野と深い理解をもたらし、互いの共有するべき体験となるのです。
これまでに挙げた作品を読むことで、さまざまな視点から世界を見ることができるようになるでしょう。それがあなた自身の視野を広げ、新たな発見を生むことを心から願っています。何よりも、読者の皆さんが、これらの物語に触れ、考え、共感していただければ幸いです。
以上、「出版業界や本に対する問題敵10選」として紹介してきた作品は、それぞれが持っている深い洞察力で我々の世界を映し出す鏡であり、問題提起の一部です。これからも、そんな素晴らしい作品たちとともに、問題を見つめ、考え、解決へと繋がる手掛かりを見つけていきましょう。
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。