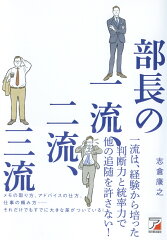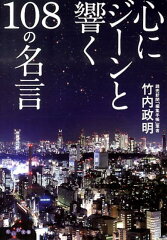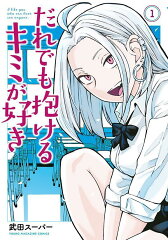ありがとう
0
この一冊は、ただの怪談集ではありません。小池壮彦氏が“怪奇探偵”として、史実と伝承の狭間を歩きながら、幽霊事件の裏に潜む「土地の記憶」や「人の営み」を丹念に掘り起こしていく、怪奇ノンフィクションの傑作です。谷中霊園、神田・お玉が池、東中野、神流湖、歌舞伎町…どれも現代の風景に溶け込んだ場所ですが、そこにはかつての事故、事件、自殺、怨念が眠っています。小池氏は現地取材と文献調査を重ね、幽霊が“出る”理由を社会史的に解き明かしていきます。その過程は、まるで土地そのものが語りかけてくるよう。本書の恐怖は、幽霊そのものではなく、幽霊を生み出した背景にあります。例えば、赤坂九丁目の米軍接収地で現れた兵士の亡霊は、過酷な訓練や自殺者の記憶が染みついた土地の声。東中野の“白い女”の幽霊も、古戦場や将門伝説が絡み合う歴史の残響。こうした“見えない記憶”が、読む者の背筋をじわじわと冷やしていきます一話一話が濃密で、地名や時代背景も複雑。関東に馴染みがある読者なら地理的な実感を持てますが、そうでない場合は“歴史の教科書”を読むような感覚になることも。それでも、夏の夜に一話ずつ味わうように読むと、まるで怪談の語り部に耳を傾けているような没入感が得られます小池氏は「怪談は真実を追うきっかけに過ぎないが、きっかけがなければ埋もれてしまう事実がある」と語ります。これは、恵里子さんの物語づくりにも通じる視点。物語は、忘れられた声を掘り起こし、語り継ぐ力を持っているのです。この本は、幽霊を“怖がる”のではなく、“理解する”ための旅。
















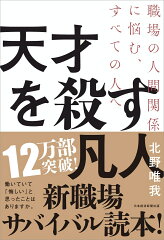


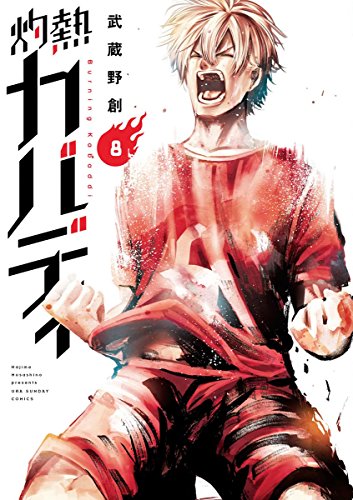


![週刊SPA!(スパ!) 2026年 1/13・20合併号 [雑誌] 週刊SPA! (デジタル雑誌)の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/5169ZMEJu+L._SL500_.jpg)

![PASH! 2026年 03月号 [雑誌] PASH!の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51uudu-9KkL._SL500_.jpg)