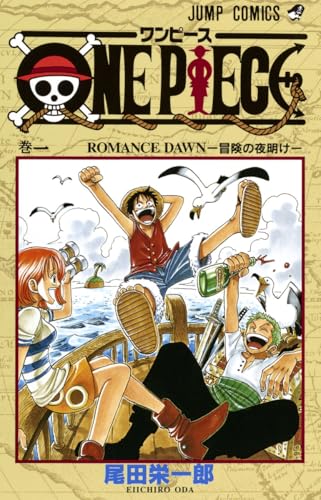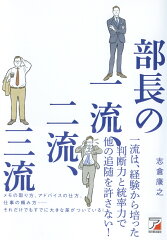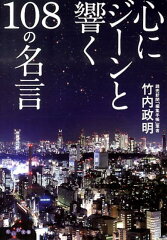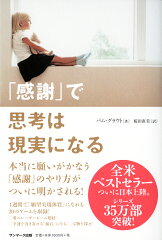ぶっちゃけ黒幕の正体は読めなかった。
中盤以降(看護師が登場するとこ)で漸く「ん??もしかして……」となるけど、ジャズを襲う試練は想像以上に過酷で残酷。なのでビリーとの直接対決からの怒涛の展開は、作中の言葉を借りるとアドレナリンでっぱなしで大興奮。
裏切られ続けたジャズの心情を思うと痛々しいですが、そんな彼を心から愛し案じ続けたコニ―と、剽軽な軽口を絶やさず支え続けたハウイー、思慮深く分別ある周囲の大人たちの存在が救い。
一巻は田舎町ロボズノットが舞台の青春ミステリ、二巻はNY舞台のサスペンスだが、最終巻でまた青春ミステリの様相が濃くなった。
父親が全米1のシリアルキラーであり、殺人の英才教育を施されたという生い立ち自体は他に類を見ない特殊さだが、「父親を乗り越える息子の物語」だと思えば、少年の成長ものとしては普遍的なテーマである。
だがこの話は単純にビリーを悪者にして終わらない。
ジャズが見る二つの夢が根底で繋がっているとわかった時はぞくぞくした。
みにくいJの「みにくい」はなるほどそういう意味も含んでたのね!と、真相を知った後ならすとんと腑に落ちる。
それにしてもこんなにイカレた黒幕は久しぶり……。
物語の黒幕として登場する狂気的な人物は、数多のフィクションで腐るほど見てきたが、終盤ジャズと対峙した黒幕が語る内容とその思考回路は本当にグロテスク。
「ジャズの人生にはビリーしかいなかったわけじゃない。ほかにもいろんな人がいて、いろんなものがあった。テレビも映画も、本も。ほかの子も、ほかの家族も。学校も。たくさんの見本があったし、お手本もたくさんいた。史上最高にお馬鹿な白人少年と、地球一セクシーなガールフレンドもね」
コニ―のこの言葉と、ジャズが「共通する部分以上に、それぞれ違ってる部分が大事だ」と語るくだりには涙ぐんでしまった……。
育った環境が人を作る。
だが環境以上に人を作るのは、人の心だ。
ジャズの生い立ちは過酷だし、親に与えられたトラウマは一生涯消えないだろうが、タナ―やコニ―、ハウイーなど、彼のことを心底案じ、手をさしのべてくれる他者に恵まれているので未来は明るい。
ラストシーンはグッドエンディングかバッドエンディングか賛否両論分かれる。
それは読んだ人がそれぞれ判断すればいいことだが、私はよい終わり方だと思った(完全なハッピーエンドとは言いにくい蛾……)
ジャズはあの人が死ぬその日まで、殺す選択はしないのだろうと確信した。
できることとすることは別である。
ましてや人が物じゃない、人は大事だと知ったジャズにとって、できることとしたいことには大いなる隔たりがある。
そしてもしジャズ自身が人は大事だと思えなくとも、ジャズを大事と、ジャスが大事だと思い続ける人々が近くにいる限り、彼は父親の二の舞にならないはずだ。
それに殺そうと思い続けるだけでシリアルキラーと同じと断定するなら、私達もシリアルキラー予備軍なのでは?
ムカツク上司にうざい同僚や同級生、うるさい家族……私達の周囲にいる、大事だと思いたくても、そう思いにくい人たち。よっぽどの聖人を除いて一度もヒトを殺したいと思った事がない者は稀だし、「いつでも殺せるんだから今日は殺さないでおこう」と自分を宥めてやり過ごす普通の人たちが、世の中なんて多いことか。
そして彼らは間違ってもビリーのような狂人でも異常者でもない。
ジャズが愛おしく踏ん張り続ける、こちら側の人間である。その大前提を忘れ、ジャズの葛藤を切り捨てた時に、私たちは本当のソシオパスに堕ちてしまうのではないか?
余談だが、タイトルは現代の方が良かった。
現在のタイトルも哀愁漂うし悪くはないのだが、原題(「血の血」)のインパクトが強すぎた。
黒幕がクライマックスで放つせりふだが、この一言にシリーズ通してのテーマ「逃れ得ぬ宿業」が集約されていて、非常に印象深い。















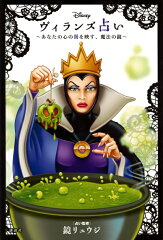
![ヤングマガジン 2026年12号 [2026年2月16日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/516Te9JKoxL._SL500_.jpg)







![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL500_.jpg)