学びの深さや面白さに改めて気づきました!問いをうまく使うことで、学びがもっと活性化するんだなと思いましたし、対話の力がこんなにも大きいとは驚きでした。大人の学びにもピッタリな内容で、すぐに実践したくなりました!
格差、政治、環境問題、キャリア、人間関係、「正解のない問題」があふれる時代に、どんな学びを届けるべきか?
延べ55万人、年間10万人以上の中高生が学ぶ探究学習、1000人以上の教育関係者(先生、管理職、指導主事等)、
企業人が学んできた研修を開発、提供する筆者が、いま必要な学びとそのデザインの手法を示す。
「問い」と「対話」のデザインによって探究学習やワークショップ形式の研修を設計していくための実践書。
まえがき 本書を手に取っていただいた方へ
序 章 いまの時代に学びを届けるということ
第1部 いま、どんな学びが必要なのか?
第1章 改めて、なぜいま学びの必要性が叫ばれるのか
学び大改革時代 / もう一つの変化 / 私たちに求められること
第2章 学びの場をデザインする前に 本書が扱う学びと理論的根拠
学び・教育に関する見取り図 / デザインと学び観・教育観のズレ / テーマとデザインの距離
/ 本書が扱う“学び” / 問いと対話による「学び観の更新」と「主体性の発露」
第2部 学びの場をどのようにデザインするか?
第3章 三段階の問いと対話の構造
前提を整える / 三段階の問いと対話の連関構造 / 「活動」と「学び」の関係
/ どんな人に学びを届けるか ニーズをとらえる / どんな学びを届けたいか 意図を紡ぐ
コラム1 学びの意図と評価
第4章 問いの力
問いの機能 / 何が問いの機能を作動させるのか? / 問いのリストを考える三つの軸
/ 「ゆらぎ」を生み出す問いの三つの観点
コラム2 学習ループと問い
第5章 対話の魅力
対話の機能 / 何が対話の機能を作動させのか? / “聞く”ということ / “違う”ということ
/ 結論を出す必然性 / おわりにー設計者の意識、学び手の意識
コラム3 問いと対話以外のデザインーグラウンドルールと環境のデザイン
第6章 問いと対話のデザイン
体験のデザイン / 対話・思考・感情のストーリー / 仮置きと磨き込み
/ 三つ目の問いと対話のデザイン / 三つ目の問いに向かう準備 / 認知的レディネスと集合知
/ 動機づけ的レディネス / 問いと問いの組み合わせの工夫 / 一つ目の問いと対話
/ 二つ目の問いと対話 / 考える手がかり / 問いの表現デザイン
/ 全体のバランスを踏まえたチューニング / 三段階の問いと対話の構造の使いどころ
コラム4“low floors” /“wide walls” /“high ceiling とerror&learn”
第7章 学びの場をどのように届けるか?
学びの場における役割 / 主体的学びが生む「隷属する主体性」と「忖度力育成」
/ オートロックのパノプティコン / 真に“私”として学べる場のために
/ 学び続ける人こそが学びを届けられる
あとがき
新着の本 すべて見る
30日間で人気のまとめ記事 すべて見る
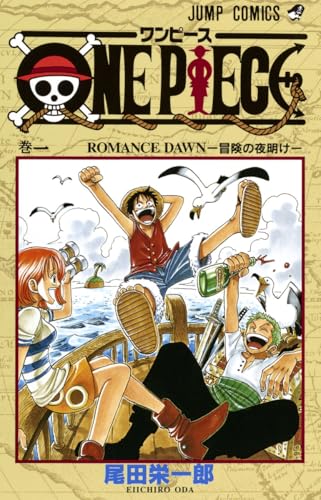





小説のまとめ記事 すべて見る

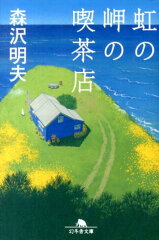




自己啓発のまとめ記事 すべて見る



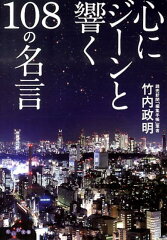

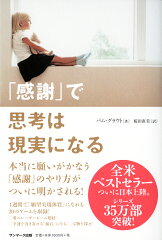
趣味のまとめ記事 すべて見る






漫画のまとめ記事 すべて見る

























![週刊少年サンデー 2026年11号(2026年2月10日発売号) [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51tim6gK0yL._SL500_.jpg)

![月刊ヤングマガジン 2026年No.3 [2026年2月19日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51+uU8-qD1L._SL500_.jpg)















