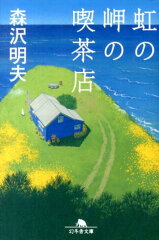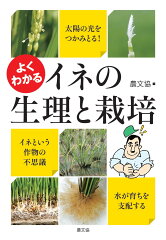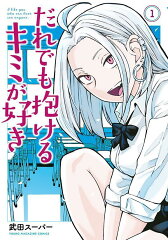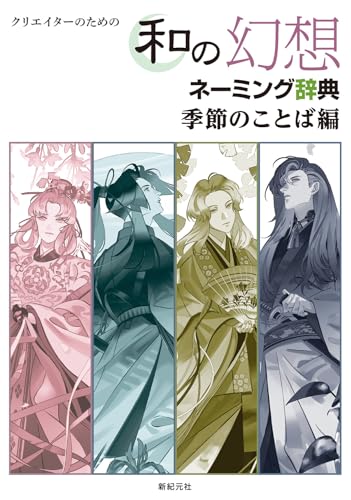謎の浮世絵師東洲斎写楽の正体に迫る本10選

皆さん、東洲斎写楽の名前は聞いたことありますか?実は彼、江戸時代の浮世絵師で正体が謎に包まれているんです。その謎を探るための本を10冊、ピックアップしました。全ての作品に共通しているのは、写楽の描く人物画の魅力を深堀りする点。現存する作品から推測される彼の人物観やリアリティに迫っているんです。さらに生涯を通じてどのような絵を描いてきたのか、彼の足跡を追います。中には、写楽の存在そのものに疑問を投げかけるものも。複数の研究者が書いた本もあるので、見解の違いにも注目してみてくださいね。驚きの新発見もあるかもしれませんよ!
『写楽殺人事件』

| 作者 | 高橋,克彦,1947- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 講談社 |
| 発売日 | 2025年01月 |
『写楽百面相』
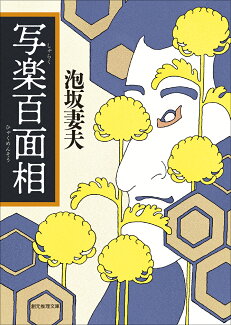
読者は最後の一行を目にした時、
改めて自らが歴史と謎の大いなる
坩堝に放り込まれていると気づき、
必ずや驚きの声を上げるであろうーー澤田瞳子(解説より)
二〇二五年大河ドラマ主人公・蔦屋重三郎の
サロンが謎を解く手掛かりに!
時は寛政の改革の頃。川柳句集の板元の若旦那・花屋二三(はなやにさ)は、馴染みの芸者・卯兵衛との逢引の折に見た、謎の絵師が描いた強烈な役者絵に魅入られる。二三がその絵師・写楽の正体を探っていくと、卯兵衛の失踪など身辺で次々と奇怪な出来事が。二三はそれらの謎も追う中で、蔦屋重三郎、十返舎一九、葛飾北斎、松平定信らと関わり、やがて幕府と禁裏を揺るがす大事件に巻き込まれる。
| 作者 | 泡坂 妻夫 |
|---|---|
| 価格 | 1100円 + 税 |
| 発売元 | 東京創元社 |
| 発売日 | 2024年09月28日 |
『写楽まぼろし 蔦屋重三郎と東洲斎写楽』

「吉原細見」や歌麿の大首絵の版元として大成功した重三郎だったが、歌麿の裏切りで苦境に立つ。代わって起用した老人・写楽の絵は大評判になったが、老人は病で死んでしまう……。蔦重と写楽の真実に迫る長編歴史小説。《解説・砂原浩太朗》
| 作者 | 杉本章子 |
|---|---|
| 価格 | 990円 + 税 |
| 発売元 | 朝日新聞出版 |
| 発売日 | 2024年11月07日 |
『写楽』

| 作者 | 皆川,博子,1930- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2020年07月 |
『寂しい写楽』

| 作者 | 宇江佐,真理,1949-2015 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 小学館 |
| 発売日 | 2013年02月 |
『写楽女』

寛政六年の春。
地本問屋「耕書堂」に住み込みで奉公している女中のお駒は、店主・蔦屋重三郎のもと、日々忙しく働くある日、店の中に入っていく長身の男を見かけた。
その男は、写楽という蔦屋が抱える新しい絵師だった。
写楽の役者絵が店に並ぶと、今まで誰も見たことのない絵に、江戸中が沸いた。
讃辞と酷評入り混じる中、突然重三郎に呼ばれたお駒は、次に写楽が描く絵を手伝ってほしいと言われ……。
選考委員満場一致で受賞した、第十四回角川春樹小説賞受賞作、書き下ろしの外伝を加え、待望の文庫化。
| 作者 | 森 明日香 |
|---|---|
| 価格 | 836円 + 税 |
| 発売元 | 角川春樹事務所 |
| 発売日 | 2024年08月08日 |
『もっと知りたい東洲斎写楽』

| 作者 | 田沢裕賀 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 東京美術 |
| 発売日 |
『憧れ写楽』

| 作者 | 谷津/矢車 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 文藝春秋 |
| 発売日 |
『からくり写楽 : 蔦屋重三郎、最後の賭け』

| 作者 | 野口,卓,1944- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 新潮社 |
| 発売日 | 2021年04月 |
『文化史よりみた東洲斎写楽〜なぜ寛政六年に登場したのか』

東洲斎写楽は寛政六年に145枚もの作品を発表し、忽然として姿を消した。その出自や本名などは謎に包まれており、これまでも葛飾北斎説、徳島藩の能役者説など、さまざまな考証が行われている。
だが、大切なのは、蔦屋重三郎の育てた歌麿と写楽の二人はどのように絡み合って画業を確立していったのか?ということである。そのために、写楽の全145作品を寛政六年に行われた歌舞伎狂言や相撲興行との関係から分析、写楽登場の社会的、文化史的背景をあぶり出す。そこには、若い日の北斎と将軍お抱え絵師の細田栄之に、名古屋の永楽屋、馬喰町の西村屋の版元としての力量がかかわっている。
現在、写楽を阿波徳島藩主・蜂須賀家お抱えの能役者斎藤十郎兵衛とする説が有力ですが、それは写楽を上層階級に位置づけたい人々の願望のあらわれです。江戸文化は庶民がヘゲモニーを掌握した庶民による庶民の文化でした。
写楽全作品145点を口絵カラーに掲載。
も く じ
口 上
一章 追善絵の謎〜歴史解題シリーズ
二章 寛政五年の蔦屋重三郎
三章 寛政六年の歌舞伎興行(三座の演目)と錦絵開版の構想
三の一、八月興行の「神霊矢口ノ渡」
三の二、上覧相撲
三の三、正月対面の場
三の四、観世の水紋
四章 東洲斎写楽と写楽の全一四五枚の構成
四の一、構成の要点
第一期;黒雲母摺の大判二十八枚
第二期;白雲母摺の大判と細判黄つぶし、鼠色つぶし(一部に舞台背景)の登場
第三期;間判大首絵の登場
第四期;桐座、都座の曽我の対面、都座の歌舞伎狂言「五大力恋ノ緘」
四の二、歌舞伎絵一三六枚をよむ前に
四の三、寛政六年の五月から閏十一月までの
歌舞伎絵一二二枚をよむ
第一期…寛政六年五月の三座(都座・桐座・河原崎座)
第二期…寛政六年七月の都座、八月の桐座
第三期…寛政六年十一月の三座(河原崎座・都座・桐座) 閏十一月の都座
四の四、間判大首絵十一枚をよむ
五章 寛政七年の旅立ち〜勝川春章の三回忌を終えて
五の一、蔦重、宣長宅を訪問
五の二、佐野川市松と奥村政信
五の三、岩佐又兵衛の「伊勢物語図絵」
五の四、市松の登場した寛保元年とは
六章 その後の東洲斎写楽
六の一、寛政七年の松平定信公
六の二、写楽への追慕
六の三、明治時代になっての評価
六の四、東洲斎写楽とはなに者か
むすび 役者絵から芝居絵へ
あとがき
| 作者 | 岡林みどり |
|---|---|
| 価格 | 2530円 + 税 |
| 発売元 | 清水書院 |
| 発売日 | 2021年08月23日 |
それぞれの作品を通じて、私たちの目には様々な写楽が描かれましたね。写楽が生きた江戸時代と、現代を繋げるかのように、私たちの想像力を刺激し続けてくれる作品たち。まさに、その不確かさが魅力なのかもしれません。
一口に「東洲斎写楽の正体」の話と言っても、その可能性は無数に広がる。写楽は一体何者なのか?その一部始終を描き切ろうとした作品もあれば、その謎を楽しむ作品もたくさんあります。
それぞれの作家は、ユーモラスに真剣に、自らの見解を作品化。江戸の風俗、生活、そして人々の生き様を描いたなかで、写楽の姿を探求していきます。もちろん、それらはあくまで創作であり、真実の写楽の姿を私たちはまだ知り得ません。だからこそ、ひとりひとりが自由に想像力を働かせられるのです。
小説や漫画の力で、いまは亡き過去の人々が息づき、時代の匂いや色彩が蘇ります。実在したかどうかも不明な写楽を描くことで、作家たちは私たち読者に「想像力の大切さ」を教えてくれているのかもしれませんね。
異なる解釈が交錯することで広がる浮世絵師・写楽の世界。未だ解明されていない謎を解き明かす喜び、過去と現在を繋げる楽しさ、古代から現代へと続く芸術への愛情。これらすべてがこの10冊には詰まっています。
ぜひ、写楽の世界を探索する旅に一緒に出かけてみてください。それぞれの視点から見た写楽の象徴するもの、それが何なのかを探し、自身の想像力を試す絶好の機会ですから。楽しい旅になること間違いなしですよ!
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。