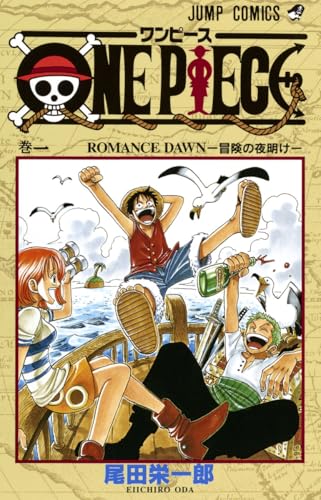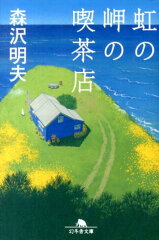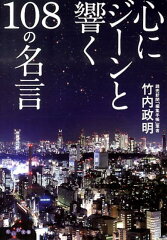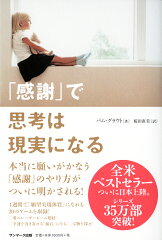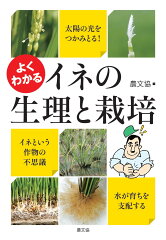邪馬台国論争の最新説が楽しめるオススメ作品10選

それでは、皆様に邪馬台国論争が織り成す壮大な物語を紹介したいと思います。ここでは、それぞれ異なる視点で論争を描いた10作品をピックアップ。一部は、歴史の孤高の識者が主人公、一部は現代の高校生がタイムスリップ。謎多き邪馬台国の存在を探ります。それぞれ独自の方法で歴史の真実に迫る姿はまるで名探偵のよう。そして物語の中には、様々な人間ドラマ、愛憎劇が織り交ぜられ、あなたの心を一瞬でつかむことでしょう。知識を深めるだけではなく、感動も得られるこれらの作品は、じっくり味わうべき逸品ですよ。
『よもやま邪馬台国 邪馬台国からはじめる教養としての古代史入門』

本居宣長、新井白石らから三〇〇年以上続く邪馬台国論争の魔力とは──?
古代日本史において、いまだ謎多き「邪馬台国」。それがあったとされる場所については畿内(近畿)説と九州説を中心に数十箇所以上もの比定地があり、百家争鳴の観がある。しかし、どの候補地も「決定打」となる物証を欠き、そのことがまた論争をエスカレートさせ今日まで古代史ファンを熱くさせている。
本書は、特定の説に偏るのは避け、何につけても「諸説あり」の邪馬台国ワールドを、ありのままに楽しんでいただくことを念頭に取材・執筆された一冊。本文中には、さまざまな説を唱える学者や在野の研究者らが登場する他、邪馬台国をめぐる「よもやま話」というタイトルの通り、取り扱う時代の幅も少し広げ、どこまでが史実か判別し難い伝承や地元に残る伝説なども取り上げる。
卑弥呼探訪の旅を通じて見えてくる、古代日本の実像。
古代史がわかれば歴史はもっと面白い!
| 作者 | 豊田滋通/著 |
|---|---|
| 価格 | 1800円 + 税 |
| 発売元 | 梓書院 |
| 発売日 | 2023年06月20日 |
『邪馬台国は大和 卑弥呼は百襲姫 歴史は捏造される』
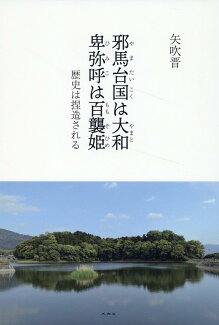
日韓併合の一九一〇年この論争は俄かに巻き起こり今なおわれわれは惑わされている 既に戦前一九二〇年代、資料を素直に読み込んだ在野の学者によって日中双方の文献学レベルでは証明されその後考古学的裏付けもなされつつある それよりはるか以前、江戸時代にも常識であったその歴史像をなぜ見失っているのか?笠井新也は『魏志倭人伝』と『日本書紀・崇神紀』中国と日本双方の史料を詳細に読み解き、一九二二、二三、二四年と三篇の論文によって地名の一致、年代の一致、行路・行程の一致、さらに人物事跡の一致を論証した。そして一八年後の一九四二年に四本目の論文を書き、墳墓の一致をも論証した。つまり文献学的研究に関する限り、ほぼ完璧に卑弥呼と邪馬台国のナゾは解明された。
| 作者 | 矢吹晋 |
|---|---|
| 価格 | 1980円 + 税 |
| 発売元 | 未知谷 |
| 発売日 | 2024年07月 |
『物理学者が解き明かす邪馬台国の謎 卑弥呼の本名は玉姫であり、邪馬台国は太宰府にあった』

鬼滅の刃の主人公・竈門炭次郎の「竈門」とは邪馬台国のことだった!
『日本書紀』と『古事記』に登場する誰が卑弥呼なのか?
1700年を経て初めて明かされる日本古代史、最大のミステリー!
卑弥呼は魏王室の外戚だった!
はじめに
邪馬台国の謎
なぜ物理学者が歴史の本を書くのか
第1章 邪馬台国の謎
「魏志倭人伝」が語る邪馬台国
卑弥呼が存在したという形跡は日本にない
なぜ卑弥呼は王になれたのか
邪馬台国の場所はどこなのか
なぜ卑弥呼は豪華な返礼品をもらえたのか
なぜ魏の王朝の鏡が日本にあるのか
第2章 なぜ卑弥呼は王になれたのか
鬼道とは五斗米道という道教の神のことである
五斗米道とはどんな宗教か
鬼道と鬼神の違い
鬼道とは五斗米道の神様=天神のこと
卑弥呼は中国五斗米道の始祖、張陵の孫である
卑弥呼の本当の名前は玉姫
卑弥呼は魏の皇帝と縁戚関係にある
なぜ「魏志倭人伝」に詳しい卑弥呼の記述があるのか
第3章 『日本書紀』と『古事記』に登場する玉依姫が卑弥呼である
玉姫とは神武天皇の母である玉依姫のことである
万世一系とは卑弥呼の子孫の物語である
卑弥呼は美人だった
第4章 邪馬台国があったのは間違いなく太宰府である
「魏志倭人伝」が邪馬台国の距離と方角を間違えた理由
改ざん前の報告書を推測する
「魏志倭人伝」の距離の記述を復元すれば太宰府に到達する
玉依姫を主祭神とする竈門神社
なぜ天神様が太宰府に祀られているのか
太宰府は九州の交通網の要所にある
出雲がなぜ古代の大都市なのか
卑弥呼の墓は大野城市にある
なぜ奈良に大和があるのか
第5章 日本の文化の礎をつくった卑弥呼
「誠の道」という日本独自の思想
二十四節気が明らかにする日本の古代史
一月中、七月中、十月中という三つの祝宴
道教国家日本
日本古代史の真実を暴いた岡田英弘氏
おわりに
参考文献
| 作者 | 下條竜夫 |
|---|---|
| 価格 | 1650円 + 税 |
| 発売元 | 秀和システム |
| 発売日 | 2022年07月16日 |
『最終結論「邪馬台国」はここにある』
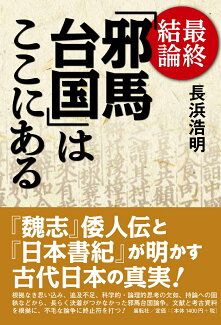
『魏志』倭人伝と『日本書紀』が明かす古代日本の真実!
根拠なき思い込み、追及不足、科学的・論理的思考の欠如、持論への固執などから、長らく決着がつかなかった邪馬台国論争。
文献と考古資料を根拠に、不毛な論争に終止符を打つ!
第一章 古代史理解のカギとは
「邪馬臺国」か「邪馬壹国」か
反面教師・NHKの虚偽番組から学ぶ
邪馬台国の「謎」解決への道
古代史理解のカギ・皇紀と実年の峻別
古代史年表はこうなる
第二章 『魏志』倭人伝の研究概史
初出・『日本書紀』神功皇后の条
「神功皇后の条」への誤認
神功皇后実在の証・七支刀
江戸時代から戦前までの論争
戦後の「邪馬台国論争」
『記紀』を無視する邪馬台国纏向説
『魏志』倭人伝=偽書説の登場
井沢元彦氏・『逆説の日本史 古代黎明編』の誤とは
井沢氏らの変節・九州説から畿内説へ
安本美典氏の「論」の検証
「卑弥呼の都」は暗くならなかった
竹内睦奏氏、「口伝」の検証
『日本国紀』の邪馬台国論とは?
百田氏の『記紀』否定と狗奴国東征論
崩壊していた「銅矛・銅鐸文化圏」論
考古学無視・百田氏の神武東征論
百田氏が着せた「神武天皇への濡れ衣」
神武東征後の大和の実態
百田氏の「応神王朝誕生説」
なぜ「継体新王朝説」を信じたか
第三章 邪馬台国は何処にあったか
「倭人」とは誰を指すか
韓国人の遠い祖先は縄文人だった
北から侵入してきた「韓民族」の祖先
こうして「帯方郡」は成立した
「倭人伝」はシナ正使のための文献である
支石墓は縄文由来だった
水田稲作の定説を覆した「菜畑遺跡」
シナ使節は何処に留まったか
伊都国の王墓と「平原遺跡」
二万戸を支えた奴国の工業力
確定している奴国までの道
渡来人とは「里帰りした倭人」である
考古学も証明「渡来人はホンの僅かだった」
突然おかしくなる不弥国への道
距離が明かす邪馬台国の位置
『魏志』倭人伝を無視する畿内論者
水行の実態とは
文化人類学的推測を加えればこうなる
邪馬台国畿内説の弱点とは
「水行十日、陸行一月」はこう読む
姿を表した山門地域の遺跡群
「七万余戸あり」の意味
理解不能な考古学者・歴史学者の解釈
「邪馬台国」山門説は揺るがなかった
第四章 「倭人・倭国」の習俗
倭人=日本人なる誤認
『日本書紀』は入れ墨をどう捉えたか
畿内説・設楽博己氏の論理破綻
女王国連合の対外窓口
百済より早くから文字を書いていた!
第五章 なぜ魏に助けを求めたか
なぜ卑弥呼は亡くなったか
卑弥呼は何処に葬られたか
第六章 卑弥呼の死後、邪馬台国はどうなったか
混乱から壱与の共立へ
邪馬台国東遷説の虚妄
吉備津彦に託した大和朝廷の方針
吉備津彦・九州遠征の目的とは
狗奴国(熊襲)が背いたわけ
『旧唐書』日本 から窺い知れるその後
なぜ、邪馬台国は「生口」を献上したか
なぜ、倭の五王は朝貢しなかったか
こうして再開した大和朝廷とシナとの外交
| 作者 | 長浜 浩明 |
|---|---|
| 価格 | 1540円 + 税 |
| 発売元 | 展転社 |
| 発売日 | 2020年07月20日 |
『魏志倭人伝の謎を解く 三国志から見る邪馬台国』
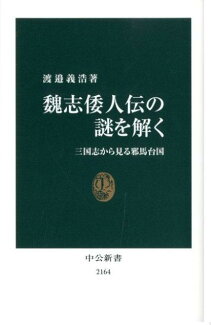
考古学調査と並び、邪馬台国論争の鍵を握るのが、「魏志倭人伝」(『三国志』東夷伝倭人の条)である。だが、『三国志』の世界観を理解せずに読み進めても、実像は遠のくばかりだ。なぜ倭人は入れ墨をしているのか、なぜ邪馬台国は中国の東南海上に描かれたのか、畿内と九州どちらにあったのか。『三国志』研究の第一人者が当時の国際情勢を踏まえて検証し、真の邪馬台国像に迫る。「魏志倭人伝」の全文と詳細な訳注を収録。
| 作者 | 渡邉義浩 |
|---|---|
| 価格 | 990円 + 税 |
| 発売元 | 中央公論新社 |
| 発売日 | 2012年05月 |
『データサイエンスが解く邪馬台国 : 北部九州説はゆるがない』

| 作者 | 安本,美典,1934- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 朝日新聞出版 |
| 発売日 | 2021年10月 |
『古墳解読 : 古代史の謎に迫る : 邪馬台国のその後、浮かび上がる大王の実像』

| 作者 | 武光,誠,1950- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 河出書房新社 |
| 発売日 | 2019年09月 |
『考古学から見た邪馬台国大和説 畿内ではありえぬ邪馬台国』
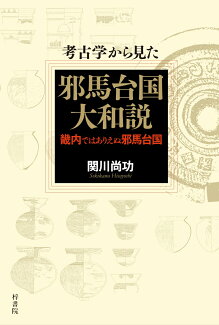
果たして、邪馬台国は「大和」にあったのか?!
古代史の中でも、特に謎が多い「邪馬台国」。
邪馬台国については、江戸時代以降主な候補地として「九州説」、「大和・畿内説」があげられる。昨今では、「大和・畿内説」が有利とみられている。
「大和・畿内説」で中心として考えられるのが、纒向遺跡、箸墓古墳である。
本書の著者は、長年、纒向遺跡をはじめ、箸墓古墳など多くの大和地域の発掘・調査に携わってきた。
そんな著者が出した結論は、「邪馬台国の存在を大和地域に認めることは出来ない」
数々の史跡、遺跡を発掘してきた著者が語る本当の「邪馬台国大和説」。
第1章 邪馬台国と大和の考古学
第2章 大和地域の弥生時代遺跡
第3章 纒向遺跡の実態
第4章 大和地方の遺跡動向と邪馬台国
第5章 箸墓古墳と邪馬台国
第6章 箸墓古墳と古墳出現年代
第7章 考古学が示す邪馬台国大和説の不成立
第8章 邪馬台国の位置と今後の行方
| 作者 | 関川尚功 |
|---|---|
| 価格 | 1980円 + 税 |
| 発売元 | 梓書院 |
| 発売日 | 2020年09月20日 |
『邪馬台国は「朱の王国」だった』
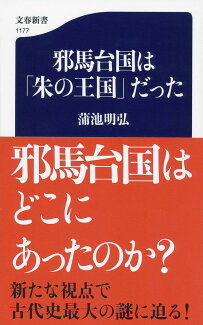
古代日本は朱の輸出で繁栄した「朱の王国」だった。
「朱」という視点で日本の神話と古代史を読みなおすと、目からウロコが!
長年、続く邪馬台国論争に一石を投じる画期的な論考の誕生。
日の丸、神社の鳥居や社殿、漆器、朱肉……と日本には朱色があふれており、この国のシンボルカラーといってもいいだろう。
朱の成分は火山地帯で産出される硫化水銀。火山国の日本では赤みをおびた石や砂として全国のいたるところで採掘できた。
朱は顔料・塗料として、防腐剤・防虫剤として、さらには不老不死をねがう薬品に欠かせない水銀の原料として、大変な価値をもっており、古代日本の重要な輸出品だった。
朱の産地が集積しているのは九州・奈良・伊勢。
そして神話、古代史には、これらの地が、いくどとなく登場する。
・なぜ神武天皇は九州南部から近畿(奈良)へ向かったのか。
・なぜ世界的にも巨大な墳墓(古墳)が奈良周辺で多く造られたのか。
・邪馬台国の候補地は、なぜ奈良と九州が有力なのか。
・なぜ八幡宮の総本社は大分県宇佐市にあるのか。
・なぜ伊勢に国家的な神社が鎮座しているのか。
・なぜ奈良・東大寺の「お水取り」は火祭りなのか。
こうした疑問も「朱」を補助線にすると、定説とは異なる解が浮かび上がる。
半世紀もの間、埋もれていた仮説を手がかりに、日本の古代を探る。
| 作者 | 蒲池 明弘 |
|---|---|
| 価格 | 968円 + 税 |
| 発売元 | 文藝春秋 |
| 発売日 | 2018年07月20日 |
『古代史入門: ~邪馬台国から平城遷都まで~ 阿波から始まる古代の軌跡』

| 作者 | 藤井 榮 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | Independently published |
| 発売日 |
さて、いかがでしたでしょうか。今回は、「邪馬台国論争の最新説が楽しめるオススメ作品10選」をご紹介しました。あなたが普段から考古学に興味があるという方もそうでない方も、こうした作品を通じて邪馬台国論争について考えてみるのはいかがでしょうか。作品によっては、その舞台や物語の背景に邪馬台国論争が織り込まれているものもあれば、キャラクターたちがその論争に巻き込まれてゆくものもあります。どの作品も精力的に取り組んでいますので、ぜひ一つでも多くの作品に手を伸ばしてみてください。
また、ただ面白いだけではなく、そうした作品を通じて歴史について学んだり、現代について考えたりするきっかけになればと思います。それぞれの作品を読み進めていくと、それぞれの作者がどのように邪馬台国論争を描いているのか、また、それが物語にどう影響を与えているのかを見つけることができるかと思います。それはまさに、自分自身がその論争の一部となり、歴史の一端を体感するような気持ちになれるでしょう。
そして、本当に邪馬台国がどこにあったのかという問いは、現代に生きる私たちにとっても興味深い問いです。歴史は決して単なる過去の出来事ではなく、現在に生きる私たちが未来を切り開いていくための羅針盤でもあるのですから。邪馬台国の場所を巡る論争に興味を持つことで、より深い歴史の理解につながることと思います。この機会にぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
それでは、さまざまな考えや視点を持つ作品たちが、あなたの読書の時間をより豊かに彩ることを心から願っています。本の世界を思う存分お楽しみください。
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。