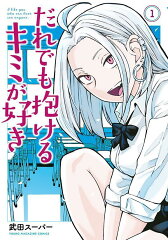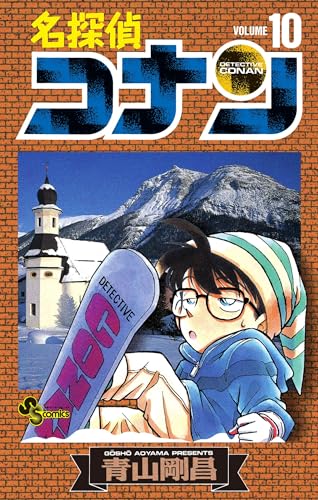自身の役割(ロール)に気づき、それに満たされた状態ーーロールフルネス。役割を与えられて過ごすうちに、自尊感情や適応感はあがってくる。高校生を対象とした実証研究から「ロールフルネス」という新しい概念を提唱する。
●著者紹介
加藤大樹(かとう だいき)
金城学院大学人間科学部教授。
2008年名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程後期課程修了。博士(心理学)。
主著に,『心理臨床におけるブロック表現技法入門』(単著,ナカニシヤ出版,2014),『ブロックとコラージュの臨床心理学』(単著,ナカニシヤ出版,2012),『スクールカウンセリングにおける投影描画アセスメント』(共著,ナカニシヤ出版,2019),『コラージュ療法』(共著,ナカニシヤ出版,2019)など。
鈴木美樹江(すずき みきえ)
愛知教育大学教育科学系心理講座准教授。
2019年名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程後期課程修了。博士(心理学)。
2011年金城学院大学大学院人間生活学研究科博士課程後期課程修了。博士(学術)。
主著に,『学校不適応感の心理学』(単著,ナカニシヤ出版,2021),『スクールカウンセリングにおける投影描画アセスメント』(共著,ナカニシヤ出版,2019),『心理アセスメントー心理検査のミニマム・エッセンス』(分担執筆,ナカニシヤ出版,2018),『子どもの心に寄り添うー今を生きる子どもたちの理解と支援』(分担執筆,唯学書房,2016)など。
第1章 ロールフルネスの背景とその誕生
1.1 はじめに
1.2 役割感からロールフルネスへ
1.3 役割とは何か
1.4 心理学的支援における役割感研究
1.5 ロールフルネス研究の展開
1.6 本書の構成
第2章 ロールフルネス尺度の作成
2.1 問題と目的
2.2 研究1:ロールフルネス尺度の開発
2.3 研究2:ロールフルネス尺度の信頼性と妥当性の検討
2.4 考 察
第3章 ロールフルネス象限モデルとロールフルネスの成長
3.1 問題と目的
3.2 方 法
3.3 結果と考察
第4章 高校生におけるロールフルネスとハーディネスとの関連
4.1 問題と目的
4.2 方 法
4.3 結 果
4.4 考 察
第5章 青年期のアイデンティティ形成におけるロールフルネスの影響
5.1 問題と目的
5.2 仮説モデルの構築
5.3 方 法
5.4 結 果
5.5 考 察
第6章 ロールフルネスが抑うつの改善に与える影響
6.1 ロールフルネスと抑うつの関連
6.2 ロールフルネス・自尊感情・抑うつの因果関係モデル
6.3 方 法
6.4 結 果
6.5 考 察
第7章 協同アート体験とロールフルネス
7.1 問題と目的
7.2 方 法
7.3 結果と考察
第8章 これからのロールフルネスの活用
8.1 学生支援の現場から
8.2 子育て支援の現場から
8.3 学校支援の現場から
新着の本 すべて見る

森に願いを

どっちにしろ、どつぼ 1

ウィッチウォッチ 8

ウィッチウォッチ 7

ホリー・ガーデン

ほどなく、お別れです

あなたが選ぶ結末は

ウィッチウォッチ 5

ウィッチウォッチ 4

ウィッチウォッチ 3

ウィッチウォッチ 2

時槻風乃と黒い童話の夜
30日間で人気のまとめ記事 すべて見る






小説のまとめ記事 すべて見る






自己啓発のまとめ記事 すべて見る


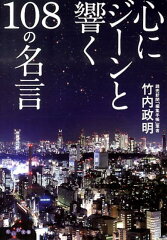



趣味のまとめ記事 すべて見る



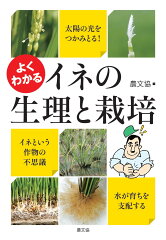

漫画のまとめ記事 すべて見る