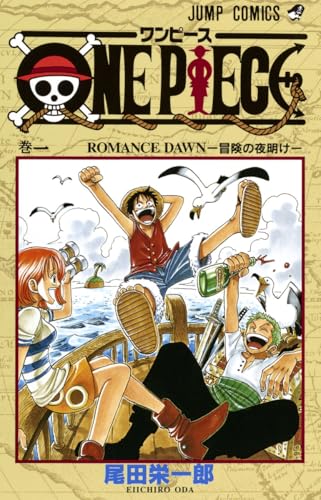『生殖記』紹介
人間の「生」を支える本能に迫る――『生殖記』は、生物学や社会学、哲学の視点を交えながら、「生殖」というテーマに正面から向き合う一冊です。繁殖行動や家族観、性的役割に関する多様な視点を提供し、現代社会の価値観を問い直します。
個人の生き方や社会のあり方を考える上で、生殖が果たす役割の重要性が浮き彫りに。繊細でデリケートなテーマを扱いながらも、科学的なデータや歴史的な背景を交えた深い洞察が特徴です。命のつながりや人間の本質に興味がある人におすすめ。この本が、新たな視点で人生を見つめ直すきっかけになるでしょう。
「共同体の拡大にどれだけ貢献するか」という物差しで、結婚や出産、多様性が評価されていく視点は、
自分自身の生き方までジャッジされているようで、読んでいて居心地の悪さと納得が同時に押し寄せます。 
それでも、大輔や樹との他愛ない時間や、小さな選択の積み重ねの中に、
「合理性」では測れないささやかな幸福の感触がにじんでいるのが救いでした。 
読み終えたあと、「産む/産まない」というテーマだけでなく、
社会から期待される役割と、自分が本当に守りたいもののあいだを、
もう一度自分の言葉で考え直したくなる一冊でした。
構成や語り口の独特さゆえに、人によっては入りづらさや戸惑いを覚えるかもしれません。それでも、読み終えた後に残る余韻と問いの重さが、この作品の大きな魅力だと感じました。個人の存在や社会との関係に疑問を持つ方にとって、とても価値ある一冊だと思います。
主人公の達家尚成、三十代の男性、同性愛者。彼はこれまで共同体から拒否されてきた経験から、すべてを穏やかに受け流す術を身につけています。
どんな組織も拡大や発展、成長を目指している中、彼はそんなことには興味がなく、何も考えずにただその場をやり過ごすことに長けています。
この物語の語り手は、なんと彼の「生殖本能」。語り口はエッセイのようにくだけていて面白いのですが、内容は非常に深く、読み解くのが難しいと感じました。わかるような、わからないような、不思議な読後感が残ります。
尚成はかなり特殊な存在であることは確かですが、「しっくりくるかどうか」を常に考えて生きている人は、案外少ないのかもしれません。多くの人は、ただ流されるままに生きているのではないでしょうか。
多様な考え方や生き方がある中で、改めて自分自身の価値観について考えさせられる一冊です。



















![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL500_.jpg)