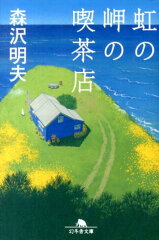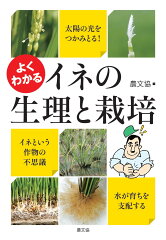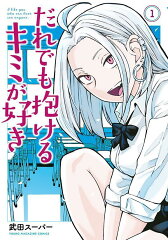古代の洞窟壁画を解説した本 おすすめ4選

古代の洞窟壁画への興味津々なら、以下の4冊は必読です。1冊目は、洞窟壁画の起源や意味、進化についてわかりやすく解説。2冊目は、フランスやスペインにある壁画の数々を豊富な写真と共に紹介し、まるで現地にいるかのような雰囲気を演出。3冊目は、壁画の制作方法や使われた道具等に焦点を当て、壁画製作の秘密に迫る。最後の1冊は、壁画の歴史だけでなく、それが人類の精神や文化の発展にどう影響を及ぼしたかを深く掘り下げた一冊。それぞれ異なる視点から洞窟壁画を解き明かすので、全て読めば一挙にエキスパートになれますよ。
『洞窟壁画考』

| 作者 | 五十嵐,ジャンヌ,1968- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 青土社 |
| 発売日 | 2023年11月 |
『なんで洞窟に壁画を描いたの? : 美術のはじまりを探る旅』

| 作者 | 五十嵐,ジャンヌ,1968- 中島,梨絵 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 新泉社 |
| 発売日 | 2021年01月 |
『洞窟壁画を旅して』

"東京芸大で美術を専攻し、さらに養老孟司の元で解剖学を学んだ美術解剖学のスペシャリスト、数多くの著作もある布施英利は、以前からラスコーなどの壁画群を見て、絵画の根源を探ろうと考えていた。そして2017年夏、美術を専攻する息子を伴い、洞窟絵画を探る旅に出た。日本の古墳壁画や星野道夫のアラスカの写真などと比較しながら、絵画の本質は何かを考察する。旅の記録とその考察が文体を変えて交互に現れ、人はなぜ絵を描くのか?という問題に迫ろうとする。
"
| 作者 | 布施英利/著 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 論創社 |
| 発売日 | 2018年09月17日 |
『最古の文字なのか? : 氷河期の洞窟に残された32の記号の謎を解く』

| 作者 | VonPetzinger,Genevieve 櫻井,祐子,1965- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 文藝春秋 |
| 発売日 | 2016年11月 |
それぞれ、その時代時代に物語っている色々なエピソードを、うまく解説してくれる本を今日は4冊ご紹介させていただきました。どの本も壁画の解釈はもちろん、それが描かれた背景や、当時の人々の生活まで紐解いてくれますので、読んでいるとまるでタイムスリップしたかのような感覚に陥ることでしょう。古代の人々が見た世界観、その思考の軌跡を追うことは、まさに冒険そのもの。神秘的で深遠なる知識に触れることで、きっと普段とは違う世界が広がることでしょう。
それぞれの本は、それぞれの視点から壁画を解説していて、その違いもまた楽しむべき点です。同じ壁画でも、一人の考古学者と一人の芸術家では、見えてくるものが全く異なるのですから。その違いを比較しながら楽しむのも一興かと思います。
さらに、壁画には、古代の人々の生活や文化がそのまま映し出されていますので、それを理解すること自体が歴史や文化への理解を深めることにつながります。決して乾いた学問だけではなく、人間の生活そのものが描かれていると思えば、親しみやすさも増すでしょう。これらの本を通じて、新たな視点から歴史や文化に触れることができれば、それが一番うれしい結果と言えます。
それでは、今日はこの辺りで。皆さんがこれらの本の中から自分に合った一冊を見つけ、歴史への興味や知識を広げていただければ幸いです。歴史を学ぶことは過去を知ることだけではなく、現代を生きる私たち自身を理解し、未来を見つめる力となるはずです。この機会に、ぜひご自身の冒険をスタートさせてみてはいかがでしょうか。
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。