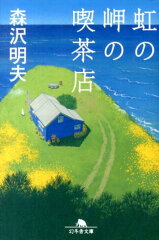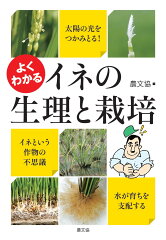細谷功の本(著書) おすすめ6選

細谷功氏の本は、多くのビジネスパーソンから愛読されている自己啓発書です。彼の作品は具体的なビジネススキルを学ぶだけでなく、人間関係や生き方について深く考えさせてくれます。独特な視点と鋭い洞察力が詰まった本6選は、読むだけでなく、日常生活に活かすヒントが満載です。しっかりとした論理的思考を身につけたい方、チームでのコミュニケーションを円滑にしたい方に特におすすめです。細谷氏の言葉には魔法があり、読者をより良い未来へと導きます。精神的にも豊かになる絶対に読むべき一冊を手に取ってみてください。
『具体と抽象』

永遠にかみ合わない議論、罵(ののし)り合う人と人。
その根底にあるのは「具体=わかりやすさ」の弊害と、「抽象=知性」の危機。
動物にはない人間の知性を支える頭脳的活動を「具体」と「抽象」という視点から読み解きます。
具体的言説と抽象的言説のズレを新進気鋭の漫画家・一秒さんの四コマ漫画で表現しています。
| 作者 | 細谷功/著 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | dZERO |
| 発売日 | 2014年11月27日 |
『Why型思考トレーニング 自分で考える力が飛躍的にアップする37問』
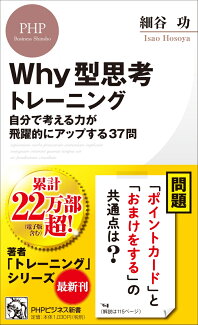
【大好評! 細谷功「トレーニング」シリーズ】
『メタ思考トレーニング』『「具体⇔抽象」トレーニング』に続く最新刊
お客様の「値段で他社に決めた」を鵜呑みにして、失敗を商品のせいにする営業マン。
自社商品のすごさをひたすらアピールする、顧客不在の「オレオレプレゼン」。
二言目には「それ前にやったことあるのか?」「実績あるのか?」といった言葉が出る「前例主義」。
「一人歩き」を始め、それを守ること自体が目的化した規則やマニュアル……。
いたるところで思考停止がはびこっているのはなぜか?
それはすべて、表面的な目に見える「What」にばかりとらわれて、その「向こう側」にある目に見えない「Why」を考えていないから。
問題解決の能力はAIが人間を凌駕していっている時代に、「Why」を考える能力はますます重要性を増している。
「AIに言われたままに生きることを望むのであれば、AIが発見した問題をAIが解決し、AIに言われるままに生きるのが人間の歩んでいく道になっていくことでしょう。このような道を歩みたい人も中にはいるかもしれませんが、大多数の人は自らの選択した人生を歩みたいと思うのではないでしょうか。そうなれば『そもそも何を解決すべきか』は人間が考えることが必須になります。そのような場合に必要になるのが能動的思考力、とりわけ人生の目的そのものを問うWhy型思考力になることでしょう」(本書「増補改訂版 はじめに」より)
Why型思考の身に付け方および活用法を説く本書を読めば、鋭いアウトプットを出すための頭の使い方がわかる。
《本書の内容》
第1章 イントロダクションーーあなたは「そのままくん」か「なぜなぜくん」か?
第2章 職場にはびこる「WhyなきWhat病」
第3章 Why型思考とは何か?
第4章 WhatとWhyを切り分ければ「世界が変わって見える」
第5章 Why型思考のビジネスへの応用例
第6章 「そのままくん」の原点はWhat型教育にあり
第7章 Why型思考を鍛えるために
第8章 Why型思考の「使用上の注意」
ロングセラー『「Why型思考」が仕事を変える』(PHPビジネス新書、2010年刊)を増補改訂し、改題。
| 作者 | 細谷 功 |
|---|---|
| 価格 | 1133円 + 税 |
| 発売元 | PHP研究所 |
| 発売日 | 2024年03月08日 |
『地頭力を鍛える : 問題解決に活かす「フェルミ推定」』
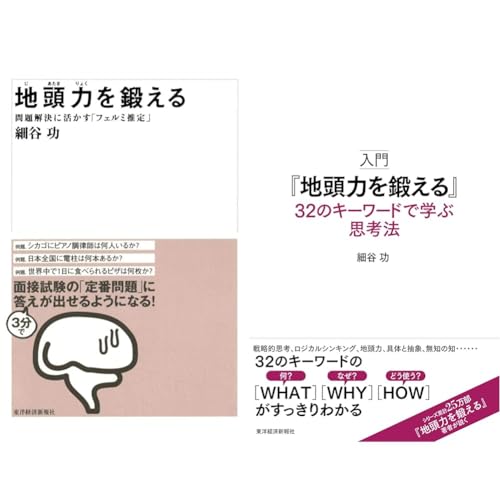
| 作者 | 細谷,功,1964- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 東洋経済新報社 |
| 発売日 | 2007年12月 |
『フローとストック : 世界の先が読める「思考」と「知識」の法則』

| 作者 | 細谷,功,1964- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2024年04月 |
『有と無』

『具体と抽象』から10年。
満を持して、シリーズ第4弾刊行!
「ある型」の思考回路は、「あるもの」に目を向ける。
「ない型」の思考回路は、「ないもの」も視野に入れる。
その両者の圧倒的ギャップが世の中を動かしている。
そのメカニズムとは?
私たちの「ものの見方」には、突き詰めれば大きく二つのタイプ、すなわち「ある型」思考と「ない型」思考がある。この両者間の「ギャップや認知の歪み」が世界を動かしている……と著者は説きます。
本書では、「世の中そう簡単に二択で表現できるものではない」という疑問にも丁寧に答えながら、「二つの思考回路」が織りなすギャップや衝突のメカニズムをひも解きます。そこからは、私たちが世の中の事象に対して抱くモヤモヤ感を晴らすヒントが見えてきます。
| 作者 | 細谷功/著 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | dZERO |
| 発売日 | 2024年06月28日 |
『「無理」の構造』

努力が報われず、抵抗が無駄に終わるのはなぜか。
本書では、「世の中」と「頭の中」の関係を明らかにし、閉塞感や苛立ちの原因に迫ります。
本書のタイトル、〈「無理」の構造〉は、〈理(ことわり)なきことのしくみ〉、あるいは〈理不尽さメカニズム〉とも言えます。
そして、本書のキーメッセージは、
「理不尽なのは〈世の中〉ではなく、私たちの〈頭の中〉である」
です。
| 作者 | 細谷功/著 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | dZERO |
| 発売日 | 2016年02月26日 |
以上、細谷功さんの自己啓発本6選をご紹介しました。細谷さんの本を一冊でも手に取ってみれば、その説得力と深みに引き込まれることでしょう。読むことで新たな視点を提供してくれ、自身の価値観を見つめ直すきっかけを作ってくれます。それぞれの本は、豊かな人間性と成功への道筋を示してくれ、これまで気づかなかった自分自身の可能性に気づくことができるでしょう。
そして何よりも、細谷さんの本は心地よい読み応えがあります。まるで心の奥深くまで響き渡るような言葉たちが、あたたかくもパワフルに私たちを突き動かします。これらの本を読むことで、まるで細谷さん自身が自分の隣にいて、温かく支えてくれるような感覚に包まれます。
どの本も一度読んだだけでは全てを理解するのは難しいかもしれません。ですが、繰り返し読むことで、その本が持っている本質やメッセージが自分の中に深く染み込んできます。普通の自己啓発本とは一線を画す、深みと重みを感じることができるでしょう。
私自身もこれらの本には多くを学び、考えるきっかけをもらいました。細谷さんの本を通して、自分自身の未来に向けた新たな一歩を踏み出す勇気をもらったと言っても過言ではありません。
あなたも細谷功さんの本を通じて、自分自身のあり方や目指すべき道を見つけ、自己に充ち溢れる可能性を引き出してみてはどうでしょうか。そして人生がより良い方向に進むきっかけとなる、素晴らしい一冊と出会えますように。この場を借りて、心よりそんなあなたを応援しています。
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。