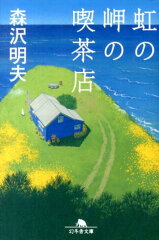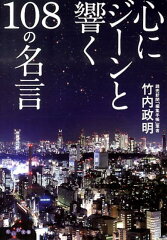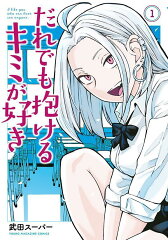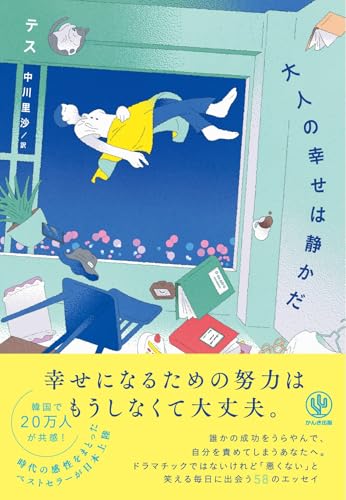擬音語・擬態語がわかる本 おすすめ6選

日本語の魅力を心ゆくまで堪能できるオススメの6冊をご紹介します。特に注目していただきたいのが、擬音語・擬態語を巧みに使う能力。どの作品も情景が目に浮かび上がるような表現が随所に散りばめられています。鼻につく匂い、心地よい風、感じたことがない経験…それらを、まるで自分が直接体験しているかのように感じ取ることができますよ。読了後には、あなたの日本語力もぐんと上がること間違いなし!自分の感じたことを言葉にする力をつけたい方に特におすすめです。
『現代擬音語擬態語用法辞典』

| 作者 | 飛田,良文,1933- 浅田,秀子,1953- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 東京堂出版 |
| 発売日 | 2018年06月 |
『オノマトペ : 擬音語・擬態語の世界』

| 作者 | 小野,正弘 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2019年12月 |
『擬音語・擬態語辞典』

日本語表現の決め手となる「擬音語・擬態語」約2000語を集大成した決定版オノマトペ辞典。用例を豊富に収載し、実際の用法も紹介。俳句・短歌の創作や、翻訳などにも役立つ。「ふっくら」と「ぷっくり」など、類義語の微妙な意味の違いも解説。「参考」欄では、「あっさり」は「浅い」からできた語、「徳利」は酒を注ぐ音「とくとく」から、など、擬音語・擬態語にまつわる歴史的背景や興味深い薀蓄も満載し、読んで楽しめる。
「しくしく痛む」と「きりきり痛む」はどう違う? 江戸時代には、鶏の声を「とーてんこー」と聞いていた?--。日本語表現力の決め手となる「擬音語・擬態語」約2000語を集大成した、決定版のオノマトペ辞典。
擬音語・擬態語の歴史的研究を開拓したことで知られ、テレビでもおなじみの編者を中心に、14人の研究者が執筆した。用例を豊富に収載し、実際の使い方、用法も紹介。俳句・短歌の創作や、翻訳などにも役立つ。
「類義語」欄を設け、「ふっくら」「ぷっくり」など、似たような言葉の微妙な意味の違いも解説。
「参考」欄では、「あっさり」は「浅い」からできた語、「徳利」は酒を注ぐ音「とくとく」から、など、擬音語・擬態語にまつわる歴史的・文化的背景など興味深い薀蓄も満載。著名マンガ家の作品に現れる用例も収録し、見て楽しめるビジュアルな編集。外国人の日本語学習者にも最適。
『暮らしのことば擬音・擬態語辞典』(2003年、小社刊)を改題し、文庫化。
日本語の擬音語・擬態語を五十音順に配列。見出し語数1385語、総収録語数は約2000語。
擬音語・擬態語の文化的な背景と歴史を知る「山口仲美の擬音語・擬態語コラム」を20本掲載。
五十音順「索引」を完備。
| 作者 | 山口 仲美 |
|---|---|
| 価格 | 2530円 + 税 |
| 発売元 | 講談社 |
| 発売日 | 2015年05月09日 |
『「感じ」が伝わるふしぎな言葉 : 擬音語・擬態語ってなんだろう』

| 作者 | 佐藤,有紀,1978- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 少年写真新聞社 |
| 発売日 | 2018年12月 |
『日本語オノマトペ辞典』
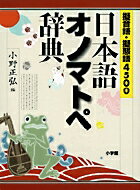
身近でよく聞く表現なのに、辞典に載っていないことば、簡単なのに、言い換えたり説明したりするのが難しいことばーーその代表格であるオノマトペ(擬音語・擬態語)を徹底的に集め、豊富な用例とともに平明に解説した本格的な辞典。 音、声、もののようすやありさまを表現するオノマトペだけで、約4500にのぼる見出し語数は類書中最大。記紀万葉から、浄瑠璃・狂言、漱石・鴎外、現代エッセイなどの用例を紹介するほか、方言としての「まったり」や「きときと」なども収録。 類義表現の使い分けや語形の似ている語群の意味・用法を解説した大小コラムや、巻末付録に漢語編・鳴き声編のミニ辞典が入って、すみからすみまで読んで楽しい1冊です。
| 作者 | 小野 正弘 |
|---|---|
| 価格 | 6600円 + 税 |
| 発売元 | 小学館 |
| 発売日 | 2007年10月31日 |
『犬は「びよ」と鳴いていた 日本語は擬音語・擬態語が面白い』

「私が一番最初にひっかかったのは、平安時代の『大鏡』に出てくる犬の声です。「ひよ」って書いてある。頭注にも、「犬の声か」と記してあるだけなんです。私たちは、犬の声は「わん」だとばかり思っていますから、「ひよ」と書かれていても、にわかには信じられない。(中略)これが、私が擬音語・擬態語に興味をもったきっかけでした。」。日本語の「名脇役」の歴史と謎に研究の第一人者が迫る。ロングセラーが待望の文庫化!
| 作者 | 山口仲美 |
|---|---|
| 価格 | 1056円 + 税 |
| 発売元 | 光文社 |
| 発売日 | 2023年05月10日 |
それでは、今回は"擬音語・擬態語がわかる本"というテーマで、私のおすすめ作品を6つご紹介させていただきました。まず初めに、これらの作品が重要なのは、日本語の魅力を引き立ててくれるからです。特に、擬音語や擬態語は、日本の豊かな感情表現や状況描写を伝える上で欠かせない要素となっています。
今回紹介した作品はどれもその魅力をうまく引き出しており、ただ単に"効果音"や"状態を表す言葉"としてだけではなく、会話文や表現の幅を広げてくれるツールとして、また知識として習得することで、言葉に含まれる感情やニュアンスをより深く理解できるようになるでしょう。
これらの本からは、言葉の深さだけでなく、日本語に対する新しい視点も学べます。例えば、擬音語や擬態語が日々の生活の中でどのように使用されているか、それぞれがどのようなシーンや感情を想起させるか。そういった事を理解することで、自分の表現力がより豊かになり、日本語の魅力を改めて感じていただけると思います。
さて、私たち自身も日々の中で擬音語・擬態語を自然と使っていますが、意識して見るとその数はなんと数千にも及びます。その多くが私たちの五感や感情を表現するために使われています。そのため、これらの言葉を理解し、使いこなすことで自分の想いを相手に伝える力が確実にアップします。
日本語学習者だけでなく、母語が日本語である方にとっても、言葉のリズムや感情表現の幅を広げるきっかけとなるおすすめの6冊でした。ぜひ一度、手に取ってみてくださいね。
そんなわけで、このコーナーもこれで終わり。次回もおすすめの本や作品を紹介しますので、楽しみにお待ちくださいね。またお会いしましょう!
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。