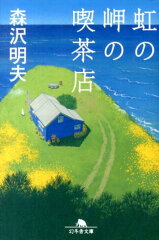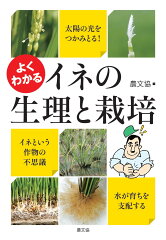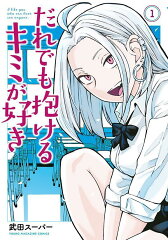平和を考える本 おすすめ6選 平和とは何か

「平和」とは何か。一人一人にとって違うかもしれませんが、それを題材にした作品は数多く存在します。ここでは、戦地の悲惨さを描きながらも、希望を失わずに平和を追い求める小説から、現代社会の問題をシリアスに考えるための社会派漫画まで幅広いジャンルから6つをピックアップしました。一部は青年から大人まで、残酷な現実を描いていますが、平和への祈りと人間の強さを感じられる作品ばかりです。それぞれの作品を通じて、平和の意味を再考しましょう。
『平和構築入門』

| 作者 | 篠田英朗/著 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 筑摩書房 |
| 発売日 | 2013年10月01日 |
『「平和」について考えよう : フロイト『人はなぜ戦争をするのか』斎藤環●ブローデル『地中海』水野和夫 井原西鶴『日本永代蔵』田中優子●ヴォルテール『寛容論』高橋源一郎』

| 作者 | |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | NHK出版 |
| 発売日 | 2016年05月 |
『平和理論入門』

| 作者 | Richmond,OliverP 佐々木,寛,1966- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 法律文化社 |
| 発売日 | 2023年11月 |
『平和をつくる方法 ふつうの人たちのすごい戦略』

★紛争研究会が選ぶ「2022年ブック・オブ・ザ・イヤー賞」最終候補作
★寄せられた賛辞の一部
「平和は可能だがむずかしい。…大きなアイデアと現場のファクト、その両方を知る専門家に耳を傾けることが欠かせない。『平和をつくる方法』は人類の最も崇高な試みについて新たな洞察を与えてくれる」──スティーヴン・ピンカー(『暴力の人類史』著者)
「セヴリーヌ・オトセールは、コンゴであれ、コロンビアであれ、アメリカであれ、日々、地域社会で暴力を減らすために努力している普通の女性や男性の物語を語る。読者に行動を促す、魅惑的で感動的な物語だ」──デニ・ムクウェゲ(2018年ノーベル平和賞受賞者)
「『平和をつくる方法』は、ありふれた国際政治の本ではない。まわりの世界の見方を変える一冊だ」──リーマ・ボウイー(2011年ノーベル平和賞受賞者)
★内容
平和構築という言葉は、私たちが何度も耳にした物語を想起させるかもしれない。ある地域で暴力が発生すると、国連が介入し、ドナーが多額の支援を約束し、紛争当事者が協定に署名して、メディアが平和を称える。そして数週間後、ときには数日後に、暴力が燃えあがる──そのような物語。
はたして、私たちに持続可能な平和を築くことなど可能だろうか? 可能だとすればどのように? そうした問いに答えるのが本書である。
著者は、善意にもとづくが本質的な欠陥を抱える「ピース・インク」と彼女が名付けるものについて──その世界に身を浸しながら(参与観察)──考察する。最も望ましくない状況であっても平和は育まれることを証明するために。
そのため、従来とは異なる問いの立て方もする。つまり、〈不思議なのは…紛争解決の取り組みが失敗するのはなぜか、ではない。ときどき大成功を収めるのはなぜか、だ〉。
そう、多くの政治家や専門家が説くのとは反対に、問題に大金を投じても解決策になるとはかぎらない。選挙で平和が築かれるわけではないし、民主主義はそれ自体が黄金のチケットではないかもしれない(少なくとも短期的には)。
では、ほんとうに有効だったものは何か。国際社会が嫌う方法だが、一般市民に力を与えることだ。地元住民主導の草の根の取り組みにこそ暴力を止めるヒントがある。そしてそれは、私たち自身の地域社会やコミュニティ内での対立の解決にも役に立つ。
本書は、20年間の学びがつまった暴力を止めて平和を始めるための実践的ガイドである。
序文(リーマ・ボウイー、2011年ノーベル平和賞受賞者)
まえがき 戦争、希望、平和
第一部 可能な和平
第一章 平和の島
第二章 ロールモデル
第二部 ピース・インク
第三章 インサイダーとアウトサイダー
第四章 デザインされた介入
第三部 新しい平和のマニフェスト
第五章 一つひとつの平和
第六章 役割を変える
第七章 自国の前線
謝辞
附録 参考資料
読書会での議論の手引き
授業の手引き
| 作者 | セヴリーヌ オトセール/山田 文 |
|---|---|
| 価格 | 2860円 + 税 |
| 発売元 | 柏書房 |
| 発売日 | 2023年12月12日 |
『平和を考えるための100冊+α』

| 作者 | 日本平和学会 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 法律文化社 |
| 発売日 | 2014年01月 |
『平和学入門 : 平和を理解するための思考のドリル 1』

| 作者 | 多賀,秀敏,1949- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 勁草書房 |
| 発売日 | 2020年05月 |
それぞれの作品を通じて、平和とは何かという大テーマについて改めて考えてみました。戦争の悲惨さを描いたもの、争いが絶えない世界での小さな希望を描いたもの、見えない敵との戦いを描いたもの、それぞれが個々の視点から平和への思いを表現しています。
これらの作品を読むことによって、一つの平和の形が見つかったでしょうか。私たちが口にする「平和」という言葉が、どれほど重く、また深い意味を持つものなのか認識する機会になったはずです。多くの人々がその意義について考え、行動する原動力になることを願います。
平和は我々全てが守るべきものであり、また求めるべきものです。その手段はいつでも我々自身の手の中にあるのです。それは単に争い事を避けるだけでなく、誤解や偏見をなくすためにコミュニケーションを取ること、理解し合うことも含まれます。また反対に、正しいと思っていることをもしも力で押し付けようとする時、それは果たして本当に平和なのか見つめ直すことも大切です。
誰しもが持っている平和への思いや願いは、どれもが独自でありながら、どれもが間違っているとは言えません。それぞれが自分の形で平和を追求することによって、より良い世界を作り上げることが可能なのです。
ぜひ今回紹介した作品たちを通して、これまでとは違った視点から平和について考えてみてください。各作品から受け取ったメッセージや感動が、皆さん一人一人の平和への思いを深めるきっかけになったら嬉しい限りです。
いつでもどこでも平和を意識することで、一人ひとりが穏やかな世界へと歩みを進められることを願っています。平和とは何か、その答えはきっと皆さん自身の中にあるはずです。
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。