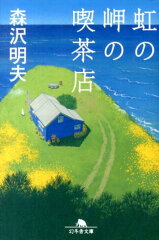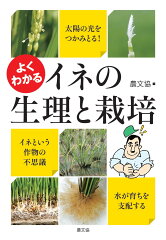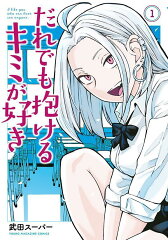美術鑑賞の楽しみ方の本 おすすめ6選

美術という空間に旅をする醍醐味を味わいたい方、今回は素敵な美術鑑賞の楽しみ方の本を6冊ピックアップしました。一冊目は初心者でも楽しめる美術入門書。美術の基礎知識からテクニックまで幅広く紹介されています。二冊目はさまざまな画派や流派の紹介を行っているので、自分の好きなスタイルを探すのに役立ちます。三冊目は美術史上の名画紹介。言葉では語り尽くせない絵画の美しさや意味を理解する手伝いをしてくれます。四冊目でアートの見方一つ一つにフォーカスを当て、五冊目は具体的な美術館めぐりのガイドブック。そして最後の一冊は、一歩踏み込んだ裏話や秘密を明かす本で、これまで見えなかった視点から楽しむことができます。 美術を深く知ることで新たな視点が開かれ、日常も豊かに感じられることでしょう。
『いちばんやさしい美術鑑賞』

「わからない」にさようなら! 1年に300以上の展覧会を見るカリスマブロガーが目からウロコの美術の楽しみ方を教えます。アートファン必読の書。
| 作者 | 青い日記帳 |
|---|---|
| 価格 | 1122円 + 税 |
| 発売元 | 筑摩書房 |
| 発売日 | 2018年08月06日 |
『論理的美術鑑賞 人物×背景×時代でどんな絵画でも読み解ける』

| 作者 | 堀越 啓 |
|---|---|
| 価格 | 1584円 + 税 |
| 発売元 | 翔泳社 |
| 発売日 | 2020年05月20日 |
『世界一わかりやすい美術鑑賞ドリル』

| 作者 | いとはる,1995- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | サンマーク出版 |
| 発売日 | 2021年10月 |
『基本の「き」からの美術鑑賞入門』

| 作者 | 田中,咲子 新潟大学大学院現代社会文化研究科 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 新潟日報事業社 |
| 発売日 | 2020年03月 |
『初老耽美派よろめき美術鑑賞術』

| 作者 | 高橋,明也,1953- 富田,章,1958- 山下,裕二,1958- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 毎日新聞出版 |
| 発売日 | 2019年12月 |
『アートと対話であなたが変わる ネット時代における美術鑑賞のすすめ』
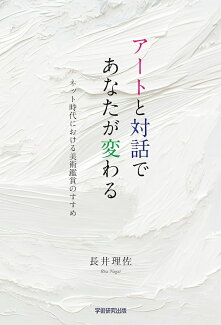
今なぜアートに向き合い対話をする場が大切なのでしょう?対話を介した協働的な美術鑑賞の研究や実践を続けてきた筆者が、インターネット・SNS時代だからこそ際立つあらたなアートの役割や対話の場の重要性を明らかにします。
現代は大手テック企業によるスマートフォンユーザーの注意(アテンション)の争奪戦に警鐘が鳴らされスマホ脳・スマホ依存なども指摘される時代です。一方、解説(情報)なしに作品をみて、心のうちに生じる感覚や思考に集中し語りあう時間は、自身の経験や知識が反映された注意を自然に働かせつつ、他者の異なる注意のありように意識を向ける“共同注意”の場をつくりだします。そこでは、注意が外からキャッチされ情報処理に追われるネット空間では得難い、スローな心身の働き(感覚・記憶・思考・想像等)に身をゆだねるマインドフルな場、いいね数による承認ではない直接的な自己承認や他者承認の場が広がります。
セルフィー的な自己や“みんな”への同調から一旦身を離し、アートを、“他者”や“異質性”に出会えるツール、長期記憶を呼び覚まし(ネットでは短期記憶のみが働きがちです)それぞれの意識のコンテンツを差異化するツール、そして、ルーティン化しがちな知覚の働きを刷新するツールとして生かすことを、作品やセッション例を交えながら提案した上で、美術を介した対話の場がAIならぬヒューマンインテリジェンスを誘発する場になりえる理由を身体性認知の観点から論じます。
| 作者 | 長井理佐 |
|---|---|
| 価格 | 1320円 + 税 |
| 発売元 | 学術研究出版 |
| 発売日 | 2023年06月19日 |
以上、「美術鑑賞の楽しみ方の本 おすすめ6選」をご紹介しました。それぞれの本には、それぞれの視点から美術を楽しむ手法が満載されています。歴史的な背景からのアプローチ、作家の思想や時代背景、美術館の楽しみ方、また、美術についての知識を深めること自体の楽しさなど、幅広い視点から美術を楽しむことができる一冊一冊には、作者の深い愛情とリスペクトが詰まっています。
どの本も、初めて美術に触れる人から、すでに美術が好きで、もっと深く知りたいという人まで、様々なレベルの読者に対応しています。これらの本を読めば、美術館へ行く楽しみが一層増すこと間違いなしです。見るだけでなく、知ることで芸術作品はもっと深く、もっと美しく見えてくるものです。読後には、あなた自身の美術への理解と興味が一層深まることでしょう。
普段あまり美術に触れる機会がない方も、ちょっとした時間に手に取ってみてください。きっと、新たな発見と楽しみが待っています。そして、それがきっかけになって、以前よりも一段と深く美術に触れるきっかけになれば、これ以上ない喜びです。
これらの本が、皆さまの美術との出会いの一助となることを心より願っております。さあ、新たな世界を、あなた自身の目で見て、感じて、楽しんでみてください。素晴らしい美術の世界が、あなたを待っています。
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。