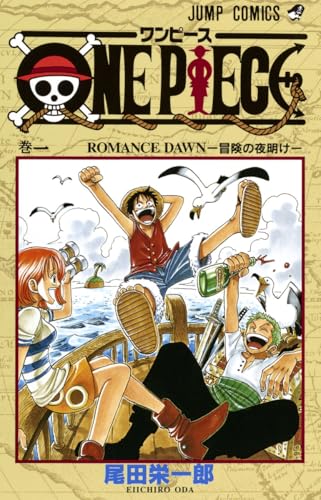年齢と小柄な見た目故にキッドとあだ名された新兵が戦場に持ち込んだのは、祖母譲りの一冊のレシピ。
彼は調理兵として、戦場の兵士たちに料理を振る舞うことになるのだが……
日常の謎というジャンルがあるが、戦争という大きな非日常の中で、ささやかともいえる謎を紐解いていく本書もその系譜に連なるのだろうか。
もちろん扱われる謎の中には決してささやかじゃない、どころかかなりの度合いで深刻なものも含まれるのだが、キッドの一人称による語り口が重苦しさを和らげている。
主人公が調理兵ということもあり、料理シーンはお腹がすく。粉末卵なんて知らない食材!林檎にソーセージをのっけただけの料理がなぜあんなにおいしそうなのか!食べたい!
人は生きてる限り腹が減るし飯を食う、戦場に行ったってその現実は変わらない。
死と隣り合わせの緊張が慢性化し、時に人間性の善良な部分を剥ぎ取らざるえない戦場下で、「料理」「食事」という日常から地続きで持ち込まれる人の営み、従来見落とされてきたエアポケットに焦点をあてたのは心憎い。
エドと個性的な仲間たちの掛け合いも軽妙で楽しく、オーソドックスな青春小説やブロマンズを主軸に据えた成長物語の趣がある。
一人一人の背景がわかり、人物像が掘り下げられるごとに、群像劇の様相を呈して物語に厚みが増すのも好み。
特にキッドの親友で、聡明で味音痴なエドの静かな存在感は特筆に値する。個人的には口が悪い衛生兵のスパークと、飄々とした美男のライナスが好き。
第二次世界大戦中の欧州(フランス・ドイツ)が舞台なので、捕虜やスパイ、ドイツ兵と恋愛関係になった女性への迫害など辛い描写も多いが、そんな中でも日々たくましく料理を作り続け、自分の信じる「正義」を貫いたキッドと仲間たちの生き様には心を打たれる。
祖母のレシピ本といい、エドの言葉といい、形をなくしても受け継がれるものは確かにあり、それが人を生かし続ける。
音楽や映画など、古き良きアメリカ色が強いので、当時の風俗や文化に興味があるひとにもお勧めしたい。
















![ヤングマガジン 2026年12号 [2026年2月16日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/516Te9JKoxL._SL500_.jpg)







![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL500_.jpg)