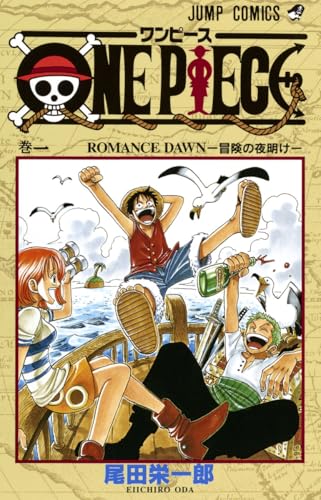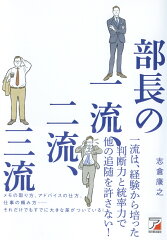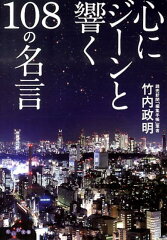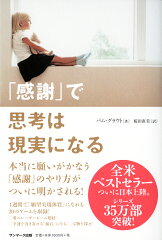「ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー」が行く先々の書店で平積み推しされてたので気になっていたが、あまのじゃくでひねくれ者の私は、その隣に一冊だけ残ってた本書を手に取ってしまった。
読書は娯楽として普段ノンフィクションは読まず主にエンターテイメントに親しんでいるのだが、読み始めたら止まらなくて、うっかり徹夜してしまった。
英国の労働者階級のさらに下、チャブやホワイトトラッシュ(白人の屑)と俗称される、生活保護受給者に焦点をあてた保育の現場を描いた話。
本書の性質的にドラッグ、アルコール、DVなど、崩壊過程出身の子供たちが多く取り上げられるのだが、悲惨な話に傾かず、タフなユーモアで貫かれているのが凄い。
時々出てくる英語に面食らうが(ラウドとか)わからないところは考えるな、感じろ。さほど難解な単語ではないので、中学校程度の英語の知識があれば言わんとすることは漠然とわかる。
そしてこの英語を所々に組み込んだフランクな文章が、非常にいい味を出している。
喩えが正確かは謎だが、イギリスの西原理恵子みたいな感じ。
地べたに転がるゴミのような現実。
なんてアホくさくて残酷だろうとあきれるしかない腐った世界でも、時にまんざら捨てたもんじゃないと思えるものを拾い、とんでもなく美しい光景を見る。
たとえばそれは片腕のない女の子が見付けた虹だったり、ブランコを蹴り出すダウン症の子の足だったり、地面に大の字で寝転がる肌の色の異なる子供たちと保育士だったり、じゃれあいながら校舎へ歩く、てんでバラバラの靴を履いた白人と黒人と東洋人の三人組だったりする。
社会問題に切り込んだ話なので移民や難民、階級差別なども取り上げられるが、私みたいな惰弱者でも一気に読めたのは、先に上げた筆者のユニークな視点とユーモアとウィットに富んだ文章、けっして綺麗ごとじゃない現実を「あなたたちは駄目なの」で思考停止せず、「の」の先を常に考え続けるアグレッシブな姿勢に感化されたから。
日本の保育問題にも章が割かれていて、一人の保育士が20人以上を見る実態が、諸外国と比べていかに過酷で立ち遅れているか思い知らされる。
常に動き回りとんでもないことをやらかす乳幼児(それも複数)を保育士が面倒見切るなんて、そりゃ物理的にも人間の限界的にも無理だ。
そんな単純で当たり前な事実、「前からずっとそこにあったのに見ようとしてないから見えず、結果ないものとされる」現実を思い知らされ、ガツンとくる。
特にやりきれない思いを抱いたのは被差別的立場の有色人種の中でも差別が起き、裕福なアジア人が黒人を無視するエピソード。
上司から部下へ、夫から妻へ、そして母から子どもへ……
同じ叩かれる立場でも相互扶助の精神が機能せず、「だけどアイツは私(俺)より劣ってる」とただの偏見を正当化することで、セルフリスペクトを保とうとする。
そんな卑しさで維持されるセルフリスペクトはもはや自尊心ではない、自尊心のまがいもの……自慰心と気付かずに。
人間って愚かだな……哀しいな……醜いな。
でも、けっしてそれだけじゃない。
根気強く絵本の読み聞かせを続ける中で、見習いのヴィッキーを認める移民の母親が一人二人と増えだすように、「人間はとんでもなく下劣で邪悪だけど、時々本当にステキなものを見せてくれるからやっぱり捨てたもんじゃないし、地べたからセカイを作りかえる価値はある」と信じられる瞬間がある。
泣くのは諦めることだから怒れ。
怯えるのはやめろ。
とてもむずかしいことだけれど、できると信じてそうしていれば、できるようになる。
スタート地点を均して完全な平等を実現するのは無理でも、そこから底上げして少しでも可能性をシェアすることはできる。
泥水を吸って咲... 続きを読む

















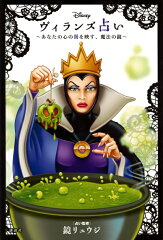
![ヤングマガジン 2026年12号 [2026年2月16日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/516Te9JKoxL._SL500_.jpg)