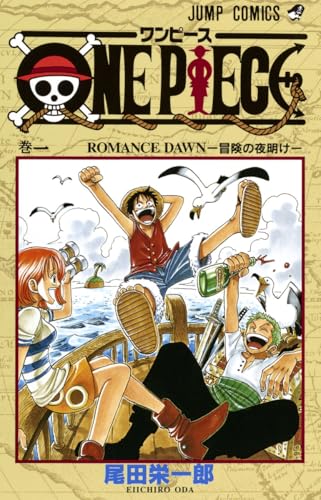文庫本で800ページを超える分厚さですが、引き込まれるように没頭して読めます。私が高校生くらいの時に、東野圭吾さんを好きになったきっかけの小説はこれでした。ドラマも観たけど、原作では雪穂と亮司が一緒にいる場面がたった1度も描かれないところがすごい。
発端となる殺人事件から19年の間に多くの伏線が張られています。一度読んだだけで伏線を回収しきることは難しい長編小説です。ミステリー好きなら、伏線を回収するのに、何度も繰り返し読み返したくなるでしょう。
読みながらずっと体温が少し下がっていくような小説でした。救いらしい救いがほとんどなくて、それでもページをめくる手が止まらない感覚が久しぶりでした。
亮司と雪穂のことを、好きだと言っていいのかずっと迷いながら読んでいました。二人がやっていることは明らかに許されないのに、そこに至るまでの背景を知ってしまうと、正義の言葉だけでは切り捨てられないものが残ります。
一番ぞっとしたのは、血や暴力の場面ではなく、二人が当たり前の顔で日常をこなしていく描写でした。白い光の中を歩きながら、その足元にはずっと暗い影が伸びている感じが、読了後もなかなか消えてくれませんでした。
物語を通じて感じたのは、真実の光と深い闇、二人の生き様が、あまりにも切なく、そして救いのない“白夜(昼とも夜ともつかない暗さ)”を彷彿とさせるその世界観でした。 
特に印象的だったのは、多くの謎と伏線が張り巡らされながらも、最後まで先が読めず、読後すぐには言葉にできないほどの衝撃と余韻が残る点です。 
総じて、『白夜行』は、犯罪と愛、罪と贖罪、人間の深い闇と、そこに潜む弱さと執念を描いた、救いようのない美しさと絶望の傑作だと感じました。
東野圭吾の『白夜行』は、幼い頃の悲劇から生き方を翻弄される男女の一生を描いた、壮大で切ない長編ミステリーです。巧妙な伏線と緻密な構成により、二人の関係や秘密が徐々に明らかになり、読む者を物語の深みに引き込みます。善悪の境界や人間の複雑な心理をリアルに描写し、悲劇的ながらも美しい結末に胸を打たれます。ミステリーとしての緊張感と人間ドラマの厚みを兼ね備えた傑作です。