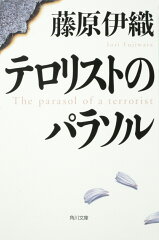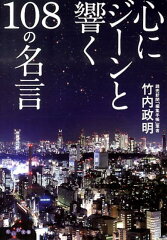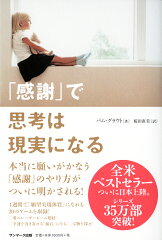素敵なタイトルだ!読み終わったら、その意味がよくわかる。一歩一歩階段を上がって行ったら、いつの間にか雲の上にたどり着いた。そんな表現をさせてくれる純粋な良い作品だ。人の成長や可能性をうまく描いている。普段の生活では言葉にして言わないことを作品の中では上手にセリフにしている。良い作品にめぐり逢えた。宮下奈都の作品はこの『羊と鋼の森』が初めてで、もっといろいろな作品を読んでみたいと思う。こんな良い小説読んだらピアノを聴きたくなるね♪
海派だけどこの本を読んでる間はずっと森のことを考えていた。どんどん大きくなっていく森に拳を握りながら入る。でも時々出てきては、また唇を噛み締めて入る人たち。主人公は森に入ってから1度も出てこなかった。
中心はどこで、今はどこだろう。私の森は、
高校生の外村はある日、一人の調律師と出会う。彼のピアノの調律を見て、音楽から景色が浮かび、彼の進路が決まる。調律師の学校に入り、調律師としての仕事をスタートした彼は、高校時代に出会った調律師板鳥の働いているお店に就職する!























![週刊少年マガジン 2026年9号[2026年1月28日発売] [雑誌]の表紙画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51jJtG5kxfL._SL500_.jpg)