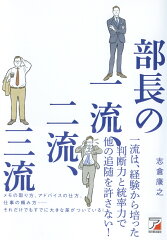縄文時代の土偶を通して、古代の人々がどのように精神的・文化的な世界を表現していたのかを深く掘り下げた一冊です。小林三千夫さんが土偶を作り手の視点から解説することで、単なる考古学的な解説にとどまらず、土偶が持つ「呼吸する精神」という独自の視点が非常に魅力的でした。縄文時代と現代をつなぐ精神的なつながりに気づかされ、過去と今がどこかで繋がっている感覚を得られます。歴史や文化、アートに興味がある人にとって、非常に深い学びが得られる本です。
この文の前半は遮光器土偶をめぐる、作り手が覗いた「縄文窯業」の物語である。縄文期の遺跡から発掘された「土製品」の多くは多種多様であり、膨大な量である。それも極めて広範囲にである。 口頭伝承文化のさなかに、拡散した縄文造形物の真意は呪術、精霊、祈念などではなく、窯業がもたらす「化学変化」を驚愕的に感知できたからである。その窯業の発端「まいぎり式」で火起こしをし、焚火の中に粘土が紛れ込み、粘土が焼成されて「焼き物」になってしまった、偶然の発見か、それに類似した出来事と推察できる。 しかも数千年を形状維持できる物質に転化し「言語」の手前のコミニケーションツールにもなった。齟齬をもたらす「方言」をしりめに社会性をもたらし、それは自由闊達に造形することに弾みをもたらした。たとえば火炎土器、尖底土器、土偶たちなどの成作意欲は半端ではなく、完成形状も舞い上がるほどの情感を持つ。これらは日本全土でシンボル化された。原始芸術という個人性を内包した特性を持っからである。
音楽芸術のように言葉のいらない「造形伝道物」は、子供も参加できる、泥んこ遊びの延長線上にありそうな、間口の広さと身近さが日本最初期の「原始産業革命」となり、現在でも「ファインセラミックス」や陶芸をはじめ数千年を、切れ目なく、おおくの陶磁器が継承されている。地上にこれほどの物質が存在するのかと思えるほど、容易く稀有な素材である。 考古学界では「土偶は壊されるためにある」とか「中空で薄手に作る土偶は壊れてしまうのは当たり前」とか窯業の初歩も知らない言動がまかり通っている。 これらを補足するため、特に系統的な遮光器土偶の「ヒト痕跡」は饒舌であり、われらが物作りと同じ刷りである事から、ほんの一片であるが、翻訳し縄文からお喋りさせた。後半では、それは現代でもすこぶる有効であることも述べた
新着の本 すべて見る
30日間で人気のまとめ記事 すべて見る
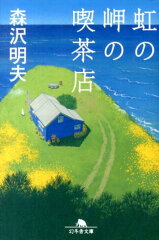

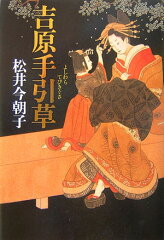



小説のまとめ記事 すべて見る
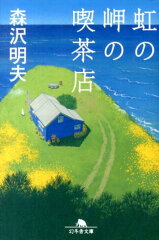


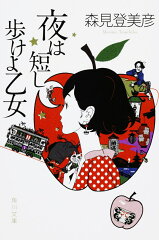


自己啓発のまとめ記事 すべて見る

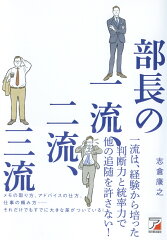




おすすめのまとめ記事 すべて見る


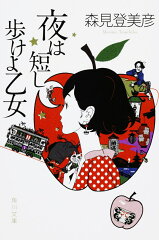

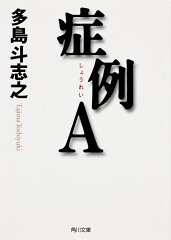

ビジネス書のまとめ記事 すべて見る