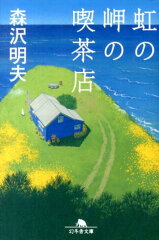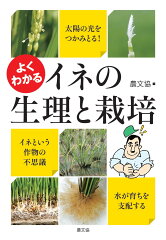読書感想文にオススメ~芸術編~

真夏の陽射しを浴びて描かれる絶品のスケッチ、それはまるでキャンバスに息づく生命そのもの。主人公の少年は、大都会の喧騒を背に、大自然と対峙し自己と向きあいます。野外での絵描きに必要な道具や技術、心構え、そんなリアルな描写も存分に楽しめます。そして、人間が持つ創作に対する無限の可能性と情熱を見せてくれます。感性を刺激し、心を揺さぶるこのストーリー、読書感想文に持ってこいですよ。芸術で人生が豊かに変わる瞬間を、ぜひ皆様も体感してみてください。
『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』

| 作者 | 末永 幸歩 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | ダイヤモンド社 |
| 発売日 | 2020年02月20日 |
『こじらせ美術館』

恋愛、家族、友人、子弟関係、自意識……
歴史に残る芸術は、偉大なる「こじらせ」から生まれた!?
ゴッホ、ムンク、シーレ、バスキア、フリーダ・カーロなど、巨匠たちのダメ人間エピソードと作品の秘密を、代表作やキーアイテムのイラスト、チャート図など視覚的要素満載でわかりやすく解説する。荻窪の「6次元」主宰、アートディレクター、金継ぎ師として活躍する著者による、美術鑑賞がもっと楽しくなる美術ネタ帳。
【目次】
●溢れる情熱と人間不信 ゴッホ
●絶望の美男子 ムンク
●女性遍歴を芸術に変えた男 ピカソ
●つながった眉毛は自由な小鳥 カーロ
●爆発する女神に育てられた奇才 ダリ
●美術史上最も愛されるジャンキー バスキア ……など12編
さらに「こじらせ人物相関図」「こじらせ画家名鑑」「コラム」も収録。
【著者】
ナカムラクニオ
1971年東京都生まれ。東京・荻窪の「6次元」主宰、アートディレクター。日比谷高校在学中から絵画の発表をはじめ、17歳で初個展。現代美術の作家として山形ビエンナーレ等に参加。金継ぎ作家としても活動している。著書に『人が集まる「つなぎ場」のつくり方』『金継ぎ手帖』『猫思考』『村上春樹語辞典』『古美術手帖』『チャートで読み解く美術史入門』『モチーフで読み解く美術史入門』『描いてわかる西洋絵画の教科書』『洋画家の美術史』などがある。
| 作者 | ナカムラ クニオ |
|---|---|
| 価格 | 1980円 + 税 |
| 発売元 | ホーム社 |
| 発売日 | 2021年05月26日 |
『東京藝大で教わる西洋美術の見かた 基礎から身につく「大人の教養」』

本書は、東京藝術大学で実際に行われている
講義に基づいて作られた西洋美術の入門書です。
通史的に作品を概説するのではなく、
著者の視点で選んだ個々の作品について、
そこに込められたメッセージをわかりやすく読み解きます。
クローズアップや補助線の導入など、
読者の理解を助けるビジュアルも多用。
楽しみながら、知らず知らずのうちに
鑑賞眼が鍛えられることを意図しています。
カルチャー・センターなどでは学べない作品も多数掲載。
1. 序章/古典古代と中世の西洋美術
ルネサンス アルプスの南と北で
2. ジョット/ルネサンスの最初の光
3. 初期ネーデルラント絵画1/ロベルト・カンピンの再発見
4. 初期ネーデルラント絵画2/ファン・エイク兄弟とその後継者たち
ルネサンスからバロックへ 天才たちの時代
5. ラファエッロ/苦労知らずの美貌の画家
6. デューラー/ドイツルネサンスの巨匠
7. レオナルド/イタリアとドイツで同時に起きていた「美術革命」
8. カラヴァッジョ/バロックを切り開いた天才画家の「リアル」
9. ピーテル・ブリューゲル(父)/中世的な世界観と「新しい風景画」
古典主義とロマン主義 国際交流する画家たち
10. ゲインズバラとレノルズ/英国で花開いた「ファンシー・ピクチャー」
11. 19世紀のローマ1/「ナザレ派」が巻き起こした新しい風
12. 19世紀のローマ2/アングルとその仲間たち
13. ミレイとラファエル前派/「カワイイ」英国文化のルーツ
14. シャルフベックとハマスホイ/北欧美術の「不安な絵画」
15. ヴァン・デ・ヴェルデ/バウハウス前夜のモダニズム
| 作者 | 佐藤 直樹 |
|---|---|
| 価格 | 1760円 + 税 |
| 発売元 | 世界文化社 |
| 発売日 | 2021年01月28日 |
『超絶技巧の西洋美術史』
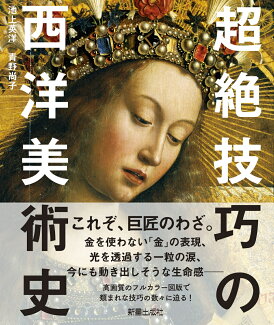
まるで本物のような質感と輝きをもつ宝石や、触り心地まで伝わる毛皮。
一本一本描かれた髪の毛に、老いを感じさせる皺だらけの肌。
あるいは、筆でざっと粗く描いただけなのに、離れて見ると本物よりも本物らしく見えてくる??。
西洋絵画を観ていると、巨匠たちの圧倒的な技巧にしばしば驚かされます。
本書が取り上げるのは、ファン・エイク、ホルバイン(子)、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ブリューゲル、デューラー、フェルメール、ベラスケス、ターナーなど、西洋美術を代表する巨匠たちの傑作群。
書籍や展覧会ではなかなか見ることのできないディテールを掘り下げ、巨匠たちの“超絶技巧”を紹介します。視覚的な面白さはもちろん、主題の意味や背景、モチーフの意味なども丁寧に解説。
ひとつひとつの作品をじっくり楽しみながら、西洋絵画の教養も一緒に身につけることができる一冊です。
○西洋絵画の傑作を高画質の拡大図版で鑑賞!
ファン・エイク《ヘントの祭壇画》、ホルバイン(子)《大使たち》、ブリューゲル《バベルの塔》、レオナルド《モナ・リザ》、フェルメール《絵画芸術》、ブロンズィーノ《愛の寓意》、デューラー《野うさぎ》、ベラスケス《ラス・メニーナス》など、傑作として知られる作品群を高画質の拡大図版で楽しめます。
○ふれられることの少ない巨匠たちの技巧に注目!
金を使わない「金」の表現、透明感と光の反射が秀逸な涙、今にも呼吸をしそうな生命感、筆を使い分けて描かれた生き物のフサフサの毛や質感、ごく小さな窓の向こうの風景描写、素早い筆致で表される立体感など、部分に注目しながら巨匠たちの並外れた技巧に迫ります。
○西洋美術に欠かせない技巧を紹介するコラムも豊富!
目を欺く「だまし絵」から、絵画の中に空間を創り出す「遠近法」、リアリズムを究めた「大理石彫刻」、高難度の技術が求められる「版画」、絵画に限りなく近い「インタルシオ」(寄木細工)まで、コラムでも多彩な超絶技巧を紹介します。
| 作者 | 池上 英洋/青野 尚子 |
|---|---|
| 価格 | 2090円 + 税 |
| 発売元 | 新星出版社 |
| 発売日 | 2022年12月15日 |
『モチーフで読む美術史』

たとえばあなたが実際に美術館に出かけて目にした、これまで見たことのない中世の西洋絵画を即座に読み解くにはどうすればいいだろうか。本書は、絵画に描かれた代表的な「モチーフ」を手掛かりに美術を読み解く、画期的な名画鑑賞の入門書である。西洋絵画だけでなく、日本を含む東洋の美術や現代美術にも言及している。人気の新聞連載に加筆し、カラー図版150点を収録した文庫オリジナル。
| 作者 | 宮下規久朗 |
|---|---|
| 価格 | 990円 + 税 |
| 発売元 | 筑摩書房 |
| 発売日 | 2013年07月 |
『クジラは潮を吹いていた。』

| 作者 | 佐藤,卓,1955- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | トランスアート |
| 発売日 | 2006年09月 |
『絵画をみる、絵画をなおす 保存修復の世界 (みんなの研究)』

| 作者 | 田口かおり/米村知倫 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 偕成社 |
| 発売日 | 2024年04月01日 |
『推し短歌入門』

⼀字のことで騒げる能⼒、対象への熱い思い、オタクは短歌に向いている!
「脚が5メートルある!」「顔がルーブル美術館(=美術品のように美しい)」などなど、オタ活においてはミームや誇張表現に頼ってしまい、語彙喪失状態になってしまいがち。
それでも、好きなものをもっと丁寧に、自分だけの言葉にしたい!
そんなオタクたちの真摯な想いに応える、現役オタク歌人による短歌入門。
| 作者 | 榊原紘/著 |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 左右社 |
| 発売日 | 2023年10月19日 |
それぞれの作品を読み終えた時、心に留まる感想は読者それぞれだと思います。しかし、無論どの作品を読んでも共通していえることではないでしょうか、それは一冊の小説や一編の漫画を通して、自分自身が未知の世界や異なる視点へと誘われることです。そして、それがまた新たな視野を拓くきっかけとなることでしょう。
特にこの度ご紹介した作品群は、日常を描くものから非日常世界を想像するものまで、様々ではありますが、それぞれに独特の視点と感性が刺激されるでしょう。また、美しい描写や深淵な心情描写を通じて、芸術的感性も豊かになることでしょう。
感想文を書くことは、読んだ作品をもう一度自分の言葉で紡ぎ直し、その際にただもう一度その世界を味わうだけでなく、個々のシーンやキャラクターへの思いや感じたことを自分なりに反芻する良い機会となります。そして、それは芸術そのものをより深く体感し、また自己の内面と向き合うプロセスとも言えます。
最後に、読書感想文はただ正解を書くためにあるものではなく、あなた自身が作品をどう捉え、どう感じたか、その深いところまで語るための存在です。それを恐れず、むしろ楽しんで、自分なりの視点や感動を素直に綴ってみてください。そうすれば、必ず読んだ作品に対する理解や愛着が深まるはずです。たくさんの作品を読み、その中から自分の感想を言葉にすることで、あなた自身が豊かな表現力を身につけることでしょう。それが、あなたが次に手にする作品を、より一層楽しむことができると信じています。
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。