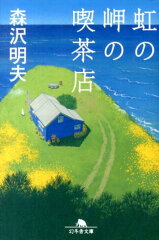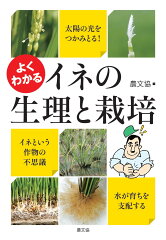夏休みに読みたい縄文時代3選!

夏休み、暑さでだるい日々抜け出し、まったりとした縄文時代にタイムスリップしてみませんか?縄文文化の魅力を描く小説から始めましょう。雄大な自然と神々を身近に感じる暮らし、日々の生活や祭り、それぞれの人間関係が生き生きと織りなす物語に引き込まれますよ。次に、子供たちの冒険を描いた漫画もおすすめ。遺跡発掘の冒険や古代への旅が子供心をくすぐります。そして最後に、縄文時代の女性たちの生き方を描く小説。彼女たちの強さや逞しさ、そして美しい心情が、現代の私たちにも響くはず。これらを手に取れば、縄文時代の風がそよぐ夏休みが待っていますよ!
『地図でスッと頭に入る縄文時代』

| 作者 | 山田,康弘,1967- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 昭文社 |
| 発売日 | 2021年12月 |
『縄文時代の歴史』

| 作者 | 山田,康弘,1967- |
|---|---|
| 価格 | 不明 |
| 発売元 | 講談社 |
| 発売日 | 2019年01月 |
『日本の先史時代 旧石器・縄文・弥生・古墳時代を読みなおす』

歴史の教科書で最初に出てくる、旧石器・縄文・弥生・古墳時代。いわゆる「先史時代」である。明治から戦後にかけ定着していったこれらの時代区分だが、考古学の発展や新資料の発掘にともない、今も定説を覆す新発表が相次ぐ。本書では、その最前線を紹介。土器の誕生、人々の定住、土偶と祭祀、水田稲作の開始、「まち」の出現、古墳の成立ーー。時代が移り変わるプロセスを重視する「移行期」研究の視点から、「日本創世」の時代の実像を描き出す。
| 作者 | 藤尾 慎一郎 |
|---|---|
| 価格 | 1034円 + 税 |
| 発売元 | 中央公論新社 |
| 発売日 | 2021年08月19日 |
それでは、縄文時代をテーマにした3作品をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。夏休みの癒しのひととき、あるいは学び深い読書の時間として、縄文時代の舞台で繰り広げられる物語をぜひ手にとってみてください。日本の歴史を生き生きとリアルに描いた作品たちからは、私たちが生きている現代の根底に流れる、人々の暮らしや考え方、文化や精神性についての新たな視点や発見があるかもしれません。
それぞれの作品は、それぞれに魅力的なキャラクターたちが織り成す様々な物語が展開します。日本を舞台にした物語ながら、縄文時代という特殊な設定は、読むひとを遠い昔の世界に引き込みます。そしてそこには、知られざる歴史の一端や、想像を超えた驚き、そして思わず心が温まるエピソードが詰まっています。
たとえば、縄文時代の人々の日常生活を深く描いた作品では、食事や衣服、住まいの作り方など、あまり知られていない生活の一端を垣間見ることができます。また、縄文時代の人々が共生していた自然との繋がりや、自然を敬う精神性を描いた作品もあります。そして、素朴で美しい縄文土器や土偶などの創造物を作り出した人々の文化と芸術性に触れる作品もあります。
そして何より、縄文時代の物語を読むことで、私たちの祖先がどのように生き、どのように考え、どのように感じていたのかを理解する手がかりになります。それはまさに、歴史と現代、そして未来への架け橋となります。
ここで紹介した3作品を、ぜひこの夏休みに読んでみてください。それぞれが独自の視点で描く縄文時代の世界を楽しみながら、自分なりの発見や感想を持つことができれば、それが最高の読書体験となることでしょう。
それでは、皆さん、素敵な読書の夏休みをお過ごしください。新たな発見があることを心から願っています。
本サイトの記事はあくまで新しい書籍と出会う機会を創出する場であり情報の正確性を保証するものではございませんので、商品情報や各作品の詳細などは各自で十分に調査した上でご購入をお願いいたします。各通販サイトが提供するサービスは本サイトと関係ございませんので、各通販サイトは自己責任でご利用ください。