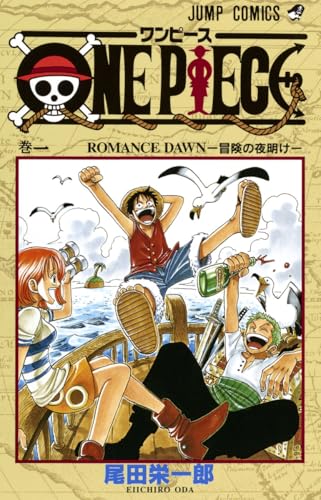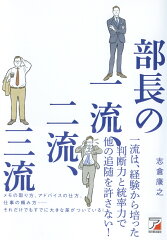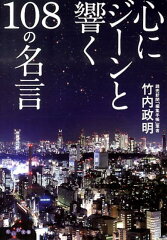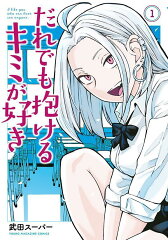kindleにて読了。
本書は、房野先生と河合先生による文通形式(往復書簡のようなやり取り)で進む解説書です。
房野先生が「超現代語訳」で噛み砕いて語り、河合先生が最新の研究に基づいて学術的に補足・解説する構成になっています。
私が驚いたのは、多くの教科書的な通念が近年の研究で覆されている点です。
たとえば、坂本龍馬が商才に長けていたことや、聖徳太子の扱いが見直されつつあることなど、目から鱗のエピソードが続きました。
とくに印象に残ったのは、豊臣秀吉の人情味と同時に見える恐ろしい一面です。
養女の病を理由に神社へ「狐を狩る」と脅したという逸話は、強烈な印象を残しました。
巻末の「おわりに」からは、お二人の「日本史を多くの人に伝えたい」という熱意が伝わってきます。本書の文体が、寺子屋で使われた往来物(往復書簡を教材にした教科書)の伝統を踏まえたものであると知り、納得しました。
代表的な往来物『庭訓往来』を思い浮かべながら、次はそのスタイルにも注目して読み返したいと思います。
さらに、河合先生が年末年始に執筆されていたという裏話も紹介されており、次に読むときはそのご苦労にも思いを馳せながら味わいたいです。
本書を通して、歴史は単なる年号や出来事の暗記ではなく、解釈や研究によって姿を変えていく“生きた学問”なのだと実感しました。