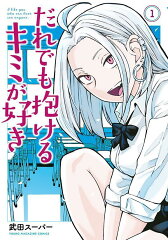この記事はアフィリエイト広告を利用しており、広告の収益で運営しています。
[PR]
記事閲覧ポイントをGET!!
ポイントガチャまであと0記事
新着の本 すべて見る

1人
罪の声

2人
ばかもの

7人
ただいま神様当番

2人
ウィッチウォッチ 13

3人
店長がバカすぎて

3人
天久鷹央の推理カルテ

2人
ウィッチウォッチ 12

3人
帰れない探偵

3人
スタート!
30日間で人気のまとめ記事 すべて見る






小説のまとめ記事 すべて見る




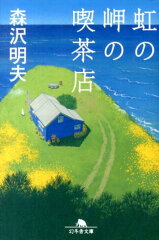

自己啓発のまとめ記事 すべて見る


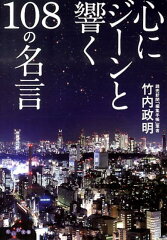



趣味のまとめ記事 すべて見る





漫画のまとめ記事 すべて見る